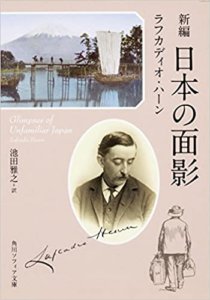小泉八雲が出会った青

藍にまつわるお噺 其の四
欧米人が夢中になった色
小泉八雲、藍と遭遇す
明治八年(1875)、明治政府の招きで来日した英国人科学者ロバート・アトキンソンは、当時の日本の街々が「藍染の青」で溢れていることに触れて『藍の説』という一文の中で、この藍色を「ジャパン・ブルー」と呼んだ。
アトキンソンから遅れること十五年、明治二十三年(1890)に、日本の土を踏んだラフカディオ・ハーン(後の小泉八雲)もまた、「藍染の青」に心打たれたひとりで、彼の著書『日本の面影/東洋の第一日目』には
「青い屋根小さな家屋、青いのれんのかかった小さな店舗、その前で青い着物姿の小柄な売り子が微笑んでいる。」
「見渡すかぎり幟が翻り、濃紺ののれんが揺れている。」
「着物の多数を占める濃紺色は、のれんにも同じように幅を利かせている。」
と興奮気味に記している。
前述のように、染物屋そのものを「紺屋」と呼んだほど、藍色は日本の色の基本だった。
ひとくちに藍といっても、一色ではない。
四十八茶百鼠、藍四十八色と言われるように多種多様の色のバリエーションがあった。
また、四十八といっても48種類しかないという意味ではなく、数限りなく多いという表現が四十八(浄土宗の四十八願から縁起が良く多いという意味とも_)となっているだけで、それ以上に存在する。
ざっと四十八種をあげても以下の色目がある。
『藍白(あいじろ)/甕覗き(かめのぞき)/白花色(しらはないろ)/白藍(しらあい)/秘色色(ひそくいろ)/空色(そらいろ)/水浅葱(みずあさぎ)/錆浅葱(さびあさぎ)/浅葱(あさぎ)/湊鼠(みなとねずみ)/藍鼠(あいねず)/紺鼠(こんねず)/錆鼠(さびねず)/水縹(水色)みずはなだ)/薄縹(うすはなだ)/浅縹(あさはなだ)/新橋色(しんばしいろ)/縹(はなだ)/青藍(せいらん)/深縹(こきはなだ)/薄藍(うすあい)/花浅葱(はなあさぎ)/薄花色(うすはないろ)/薄花桜(うすはなざくら)/花色(はないろ)/藤納戸/ふじなんど)/納戸(なんど)/高麗納戸(こうらいなんど)/錆鉄御納戸(さびてつおなんど)/錆御納戸(さびおなんど)/御召御納戸(おめしおなんど)/鉄御納戸(てつおなんど)/鉄(てつ)/熨斗目花色(のしめはないろ)/藍(あい)/濃藍(こあい)/藍錆(あいさび)/紺(こん)/紺青(こんじょう)/鉄紺(てつこん)/紺藍(こんあい)/藍鉄(あいてつ)/搗色(かちいろ)/青搗(あおかち)/紫紺(しこん)/茄子紺(なすこん)/搗返し(かちがえし)/留紺(とめこん)』
もともと日本で藍や茶、鼠の渋めの色目のバリエーションが増えたのは、江戸幕府がたびたび発令し、庶民の贅沢を抑制した〝奢侈禁止令〟にある。
奢侈禁止令では、庶民の着物の素材に麻か木綿、染め色に藍・茶・鼠などの色以外の使用を禁じたため、この三色のバリエーションが豊富となり、色に対する感性や染色の技術が鍛錬されたとも捉えることができる。
制限や縛りが多くなることで、そこに職人の創意工夫が生まれ技が成熟する、歴史の妙である。
 「楽屋正月の図」豊国 画/早稲田大学演劇博物館 蔵
「楽屋正月の図」豊国 画/早稲田大学演劇博物館 蔵
五人の役者の見事な渋い藍色の着姿
小泉八雲が来日した明治初期は、街中に藍四十八色、四十八茶百鼠が溢れ百花繚乱であった、その色々たちに彼は出くわし感嘆したのである。
しかし、皮肉なことに、小泉八雲が藍色に感銘を受けたこの明治中頃から、ドイツで開発された安価な化学染料の合成藍が大量に輸入されて、日本の天然藍は急激に衰退していく。
日本民藝の父、柳宗悦(むねよし)は、これを「近世の日本染織界に起こった一大悲劇」として、
「日本人は、人造藍で便利さを買って、美しさを売ってしまいました。」
「色は本藍ほどに丈夫ではありませんし、使えばきたなく褪せてゆきます。それに何より取返しのつかないことは、天然藍が有(も)つ色の美しさを失ってしまったことです。化学は人造藍の発明を誇りはしますが、誇るならなぜ美しさの点でも正藍を凌(しの)ぐものを作らないのでしょうか。それは作らないのではなく、作れないという方が早いでありましょう。この点で化学は未熟さを匿(かく)すことは出来ません。」と嘆いている。
ここに〈科学の進歩と人類の進化、真の豊かさとは何か〉を考えさせられる。