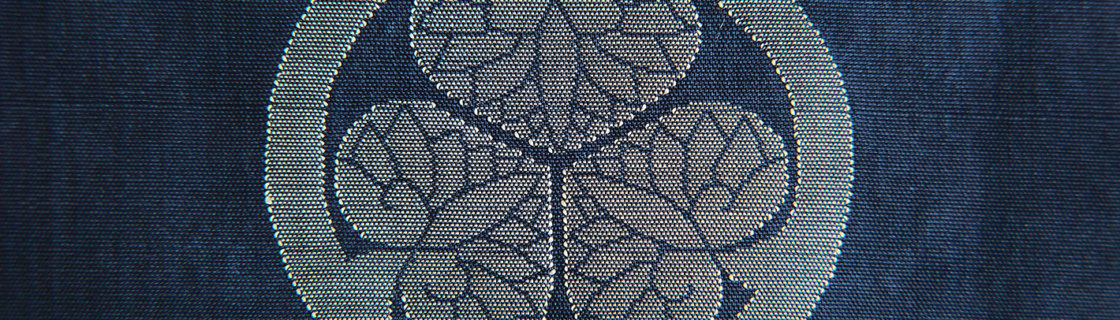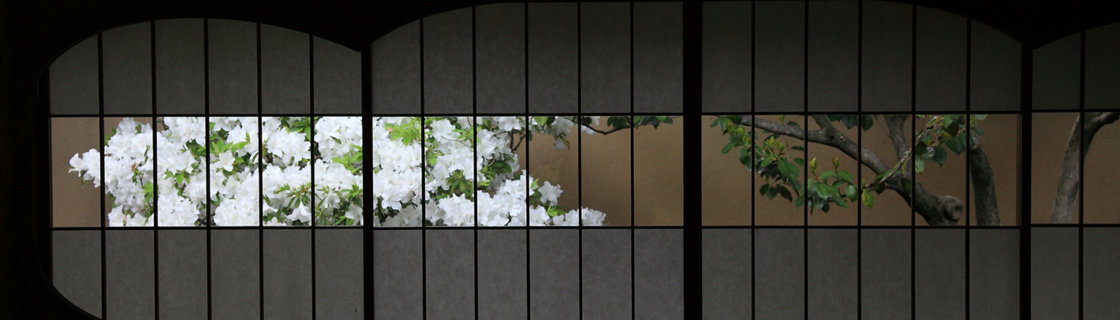前野曜子

昭和歌謡_其の三十六
洋楽カバー曲について想う
『ハッシャ・バイ』から『別れの朝』へ
前回、昭和歌謡の大ベテラン歌手、現役最長老の旗照夫について書きました。
私の出身高校の同窓生の、大先輩である旗照夫先生の「看板ソング」といえば、オリジナル歌謡曲の『あいつ』と、洋楽カバー曲の『ハッシャ・バイ』というのが、昭和歌謡史の〝常識〟だったりしますが……。
ハッシャ・バイ
この『ハッシャ・バイ(Hush a bye)』は、有名なジャズのスタンダード・ナンバーで、先生は1954年に、この楽曲のカバー(訳詞:藤浦洸)を引っさげてデビューしました。このシングルレコードは大いに売れまして、若手〝イケメン〟ジャズシンガーの旗照夫は、一躍、お茶の間の人気者になります。
同時期に、ダークダックスやペギー葉山も競作でレコードを発売しましたが、昭和歌謡史において『ハッシャ・バイ』といえば、イコール旗照夫の〝持ち歌〟です。原曲は、アメリカ南部の伝統的な黒人の子守歌『All the Pretty Little Horses』なんだそうで、要するに、これは子守唄です。
子守唄を大人の〝耳〟にも馴染むポップス風、歌謡曲風にアレンジし、恋人の男性が、愛しい女性の耳元で、甘く優しく囁きかけるように唄う……という趣向の名曲には、わが国初のドゥーワップ系の歌謡グループ、キングトーンズの大ヒット曲『グッド・ナイト・ベイビー』(1968年5月1日発売)がありますね。
ドゥーワップの説明は、けっこう厄介で長くなりますから、またの機会に譲りたいのですが、乱暴にいえば、黒人が教会で唄うゴスペルの形態。日本では、鈴木雅之率いるラッツ&スター(元のシャネルズ)が、このスタイルでした。もっとも鈴木は、子供の頃に人気だったキングトーンズに魅せられて、自分でグループを結成したわけですが……。
『ハッシャ・バイ』も、趣向自体は『グッド・ナイト・ベイビー』とまるっきり一緒でありまして、歌詞を〝そのまま〟読めば、ママが愛しい坊やを寝かせるための、明らかな子守唄でしょうが、どっこいこれが、かつて「魅惑のスイート・ボイス」と称賛された、旗照夫の艶っぽくムーディーな声で囁くように唄われれば、女性はイチコロ!! そのままベッド・インてなことに(笑)。
ダニー・トーマスが主演した映画『ジャズ・シンガー』(1952年公開)の中で、ペギー・リーとミルドレッド・ダンノックが唄ったのが、『ハッシャ・バイ』でした。
さて『ハッシャ・バイ』にかぎらず、戦後の歌謡曲全盛期、特に1950年代~60年代にかけて発売された、かなりの数のヒット曲が、洋楽のカバーだったりします。江利チエミのデビュー曲『テネシーワルツ』や、そのB面に吹き込まれた『カモナマイハウス』(1952年発売)、雪村いづみの『オウ・マイ・パパ』(1954年発売)や『青いカナリア』(1954年発売)ほか……。
なぜ、日本の歌謡曲のジャンルで、洋楽のカバー曲がもてはやされるのか? 答えは簡単です。日本人は欧米文化、特にアメリカンカルチャーが大好きな国民だからです。第二次大戦で、あれだけ痛めつけられ、悲惨な想いをさせられているのに、なぜか日本人は、すぐにそんな〝過去〟は忘れ、アメリカ人がやること為すこと、片っ端から憧れ、真似したくてたまらないんですよねぇ。
戦時中、小学生だった私の母親は、毎日毎日、学校へ行くと授業もそっちのけ、竹槍を持たされ、天に向けて、思いっきり「エイヤー!!」と突き上げることを教師に命じられたそうです。
「お国の勝利のため、憎っくき鬼畜米英の、すべての戦闘機を撃ち落とすべく、機体の腹に向けて、魂を込めて竹槍を突きまくれ~ッ!!」
戦後、鬼畜のはずの米兵が投げてよこした、チョコレートやらソーセージの缶詰やらの美味に、すっかり腑抜け、オツムがやられちまったのでしょう。もっとも〝それ〟こそが、アメリカ軍部の狡猾な戦略だったわけですが。
まぁ、ともかく世界広しといえども、日本人くらいアメリカンカルチャーに、よだれを垂らして憧れる国民も、先進国の中では珍しいでしょう。その風潮は、文明開化の鹿鳴館の〝あの当時〟から、どれほど日本が経済的に力をつけようが、まるっきり、何ひとつ、嫌になるくらいに変わりません。
目ン玉が青い外人に、「日本って、どうして○○なの? アメリカじゃ考えられないよ」とボヤかれりゃあ、本来ならば、その外人に「日本はかくかくしかじか、こういう国なの。アンタも日本に長く居続けたいなら、いい加減、日本のカルチャーに慣れて!!」と教え諭すべきところを、わが国古来よりの伝統的風習の方を、「グローバル的に時代錯誤だ」とかなんとか、冷や汗かきながら、即座に取りやめてしまう。変えてしまう。これはもう、幼児性丸出しの、愚かなコンプレックスとしか言いようがない。
令和天皇の晴れがましい即位の祝典においても、そうです。日本国の象徴たる天皇陛下なのですから、わが国伝統の美しく格調のある装束で、上から下までビシーッ!! と決めていただきたかったですねぇ。なんで洋装なの? いくら格好つけたところで、英国貴族には敵わないでしょうが。皇室でさえ〝そう〟なのですから、和装の文化が淘汰されるのも、時間の問題と言わざるを得ません。
そして何より、日本人の欧米文化コンプレックスの骨頂が、音楽の世界でありまして……。特に歌謡曲のジャンルは、どこを切っても洋楽コンプレックスの塊で成り立っている!! と言っても暴論じゃあないはずです。
昭和歌謡も平成POPSも、この理屈において、さほど変わりません。音楽関係者の心理とすれば、楽曲を唄う歌手はもちろん、『音創りの現場』の空気そのものが、昔も今も「アメリカ最高!!」「イギリス最高!!」という意識で埋め尽くされているようです。
明治の初頭に、義務教育のカリキュラムのうち、音楽の授業を取り決める際、当時の文部省の官僚どもは、すっかり欧米の教育関係者の考えに洗脳されちまったんですね。やつらに命じられるまま、日本伝統の音楽=邦楽文化をあっさり捨てて、「もっぱら五線譜で書かれた洋楽で授業を行うべし」……と決まってしまいました。(※この話は長くなるので、別の機会に回しましょう)
話を『ハッシャ・バイ』に戻しますが、当時の洋楽カバー曲はどれもこれも、原曲どおりの英語の歌詞と、日本語に訳した歌詞とを、〝チャンポン〟にして並べているだけです。
♪~ルルラルル ぼうや おねんねなさい
やさしいママの むねのなかで
(中略)
Mama won`t go away
Sleep in my arms
while you still can~♪
もっと〝チャンポン〟がリアルなのは、江利チエミの看板ソング『テネシーワルツ』ですかね。
♪~I was dancin’ with my darlin’ To the Tennessee Waltz
When an old friend I happened to see
I introduced her to my loved one And while they were dancin’
My friend stole my sweetheart from me.
さりにし夢 あのテネシーワルツ なつかし愛の歌
思い出偲んで 今宵も唄う うるわしテネシーワルツ~♪
英語と日本語の〝チャンポン〟の歌詞ではなく、オリジナルの昭和歌謡と同じく、歌詞の日本語が、ごく自然な形で洋楽のメロディにフィットし、なんの違和感もなくリスナーの耳に歌詞が届く……ような楽曲となると、作詞家の側に、それ相当の腕とセンスが要求されます。
たとえばコーちゃんこと越路吹雪が唄って大ヒットさせた、『ラストダンスは私に』(1961年11月発売)や『ろくでなし』(1965年7月発売)などは、元歌が有名なシャンソンであることを知らなければ、越路吹雪のオリジナルソングだと信じて疑わないでしょう。それほど日本語の歌詞が、メロディにピッタリ〝ハマって〟います。
♪~古いこの酒場で たくさん呑んだから
古い思い出はボヤけてきたらしい
私は恋人に捨てられてしまった 人がこの私を札付きと云うから
ろくでなし ろくでなし なんてひどい アーウィ!! 云い方~♪
ううむ、あまりにみごとな日本語の〝並び〟ですね。
岩谷時子という、天才的な作詞家だからこそ、「当たり前に」こういう日本語が、次から次へと紡ぎ出せるのでしょう。
岩谷がオリジナル歌謡を量産し、売れっ子作詞家になる前、膨大な数のシャンソンの訳詞を手がけました。それまでの日本の歌謡曲にないメロディやリズムに、日本語の歌詞を当てはめる際、どんな文言をどういう順に並べたら良いか? さんざん研究に研究をかさねたからこそ成せる、職人芸ともいうべき〝仕事〟です。
別れの朝
岩谷と並び、もう1人、洋楽カバー曲の歌詞を、オリジナルの歌謡曲ばりに仕立て上げることが叶う、プロ中のプロの売れっ子作詞家といえば、なかにし礼です。彼は立教大学の仏文科出身で、学生時代から、すでにシャンソンの訳詞の〝上手さ〟では定評がありました。
石原裕次郎との運命的な出逢いを経て、裕次郎がプロデュースする格好で、ロス・インディオス&裕圭子が歌唱する『涙と雨にぬれて』(1966年発売)というムード歌謡で、洋楽カバーではなく、オリジナルの歌謡曲の作詞家としてデビューを果たしました。
彼が放つ日本語のリズム、七五(五七)調の言葉の〝並び〟は、これはもう、持って生まれたセンスとしか言いようがありません。要するに、日本語の扱いが〝上手い〟んです。
それを証明するかのような1曲が、カラオケファンなら一度は唄ったことがあるはず。ペドロ&カプリシャスの(メジャーとしての)デビュー楽曲『別れの朝』(1971年10月発売)です。昭和歌謡史に遺る名曲中の名曲であり、レコードも56万枚近く売れた、大ヒット曲です。
♪~別れの朝 ふたりは さめた紅茶 のみほし
さようならの くちずけ わらいながら交わした
別れの朝 ふたりは 白いドアを開いて
駅につづく 小径を 何も言わず 歩いた~♪
皆さんにお馴染みの、この有名な歌詞。じつはこの楽曲が、オリジナルの歌謡曲ではなく、オーストリアの歌手であるウド・ユルゲンスの『Was ich dir sagen will(邦題は、夕映えの二人)』のカバーであると、ご存じない方も、大勢いらっしゃるのではないでしょうかね。
かく言う私も、同じくです。膨大な数の歌謡曲を聴きまくってきた私でさえ、なかにしが紡ぎ出した日本語の歌詞が、メロディに〝ごく自然〟にフィットしているため、てっきり筒美京平か川口真あたりの、ビッグヒットメーカーの作曲家の〝仕事〟だと、長いこと勘違いしておりました。
歌謡曲マニアの中には、「洋楽カバー曲の歌詞は、訳詞のセンスがよろしくなく、どれもこれも陳腐だ」と、愚弄される方も多いのですが、どっこい「そうでない」楽曲もぽつり、ぽつりと存在します。
そして、そのクオリティの高さこそが、洋楽だけを聴いて育って来たような、若い世代の〝耳〟をも唸らせ、令和の時代にまで受け継がれる、カラオケの〝定番曲〟として成り立たせているのではないでしょうか。
ちなみに『別れの朝』は、ペドロの女性ボーカルが〝初代〟前野曜子の時代の楽曲です。彼女が40歳の若さで亡くなったこともあり、〝2代目〟高橋まり(現在は真梨子)は、ソロデビュー後、しばらくの間、「『別れの朝』は前野さんの持ち歌だから」と、ライブなど人前で歌唱するのをNGにしていました。
![]() 勝沼紳一 Shinichi Katsunuma
勝沼紳一 Shinichi Katsunuma

古典落語と昭和歌謡を愛し、月イチで『昭和歌謡を愛する会』を主催する文筆家。官能作家【花園乱】として著書多数。現在、某学習塾で文章指導の講師。