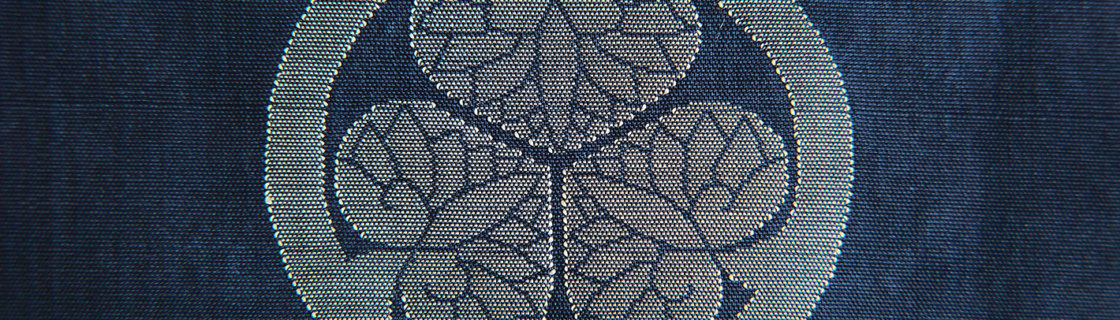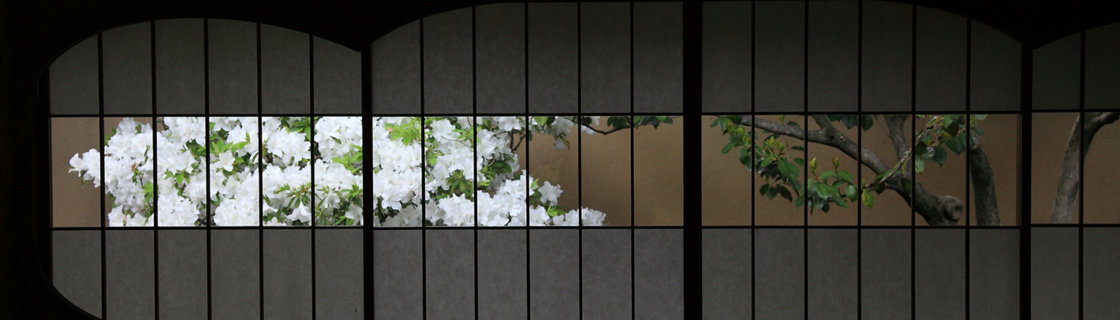長谷川きよし 前編

昭和歌謡_其の五十
春が来れば想い出す。「親父の命日と長谷川きよし」【前編】
『黒の舟歌』
令和2年めの冬は、暖冬だそうですね。例年「雪国」と称される地域に住まわれる皆さんにとって、今年はずいぶん生活も楽になるだろうなぁ、
などと単純に考えてしまうところが、都会でしか生活したことのない人間の、想像力のなさでありまして、当地には当地なりに、豪雪の被害と背中合わせの〝恩恵〟も、多々あるのだ、という内容のコラムを、先日、某新聞紙上で拝読しました。
確かに、全国のスキー場は、滑走するに満たぬ雪の量では、商売上がったり!! でしょうし、「美味しい天然氷」を全国の飲食店へ出荷している業者(現在では、ほんのわずかになっているようですが)も、通常どおりに氷が〝出来上がらず〟、途方に暮れている様子です。
令和2年の2月4日、立春。暦の上では、春の到来。このあたりの〝お話〟は、当メルマガの主宰者にお任せするとして、
個人的に私が信奉している占いが2つありますが、どちらの〝但し書き〟にも、「占術の世界では、新しい年の始まりは、1月1日ではなく、立春の2月4日です。毎年、節分(2月3日)から立春にかけて、暦が一変するとともに、運気も大きく変動するのです」……とあります。
私にとっての立春は、実の父親の葬式を執り行った日として、記憶されています。死んだのは平成15年(2003年)1月30日の未明、場所は都内のど真ん中、東京タワーの真下にある芝公園の草むらでした。
まともな死に方であるはずがありません。メチャメチャ寒い夜で、都内でも昼間から雪がちらつき、気温もマイナス2度ぐらいまで下がっていましたね。路上生活者にとっては、ひとたまりもなかったでしょう。要するに凍死です。文字通りの〝野垂れ死に〟。
でも、私は少しも驚きませんでした。むしろ幼い頃から想像していた通りの、親父の最期でありまして、志していた「偉大なる文学者」としての生涯は叶わなかったにせよ、死に様だけは立派に、親父が追い求めた文豪たちと、同じ道を選んだ、というわけでしょうかね。
つい昨日のことのように、〝あの日〟の出来事をリアルに覚えておりますが、早いものですねぇ、今年で17回目の命日がやって来ました。物書きの端くれとして、〝あの日〟のことを小説作品に仕上げ、何年も前に、某同人誌に掲載させてもらいました。
タイトル『Identity ―われおもふゆへにわれあり―』
ハズカシナガラ、ちょいと親父の供養のつもりで、以下、少しだけ転載させていただきます。主人公は、私がモデルの矢沢恭一、親父の名前は一寛(いっかん)です。
★ ★ ★
のたれ死になどという人生の最期は、小説や映画やドラマ、芸能ゴシップ記事などに登場する出来事としては、ある種の「わかる人にだけはわかる」あやしく仄昏(ほのくら)い輝きを放ってもいるのだろう。しかし、あくまでフィクションではない、現実にそうされた身内の立場となれば、情緒的にとらえてばかりもいられない。
恭一はかなり以前から、一寛のそういう末路を予測していた。もっといえば、そういう死にざま以外、神様がお赦(ゆる)しにならないはずだという、はなはだ底意地の悪い懲罰的な期待をずっと抱いて生きてきた。
ところが実際に警察署から遺体確認のための連絡を受けた時、オハズカシナガラ単純にたまげてしまった。正直、動揺もした。親父が急死したことへの気持ちの揺れではない。人間サマが一人、真冬の公園の草むらで凍死することは「本当に起こり得るんだな」という、けったいな感慨にほかならない。
それにしても世の中に、実の父親の晩年の商売がサラ金および風俗店のサンドイッチマンであり、最期がのたれ死に、という現実を体感させられる子供って、どのくらいの数いるのだろう?
一寛はおよそ五年ほど、猛暑の夏も極寒の冬も、毎日毎日、JR山手線の神田駅の改札を抜けた交差点付近にて、ひたすら大判の看板を支えつつ立ち尽くした。
★ ★ ★
親父は幼少時代から、こと文学に関してのみ早熟の才を発揮したらしく、大学時代には、著名な文芸評論家・吉田健一(かの吉田茂首相の息子)に師事しました。自分も評論家として文壇デビューする予定が狂い、なかなかその夢も叶わぬまま、幼馴染のお袋と結婚し、長男の私と妹が生まれ、生活のために〝不本意ながら〟銀座にある広告会社のコピーライターになったのです。
幸い、仕事は「出来る」タイプだったようで、時代もちょうど民放テレビの開局ラッシュ!! さまざまなスポンサーからのコピーの注文に追われ、会社員としては、かなりの報酬を稼いだはずですが……。
そのカネの〝ほぼすべて〟を、毎晩のはしご酒と帰宅のタクシー代に使い果たし、私の記憶として、親父から小遣いをもらったことは、たったの一度もありません。世間の流れどおり、お袋には離縁され、享年67歳まで、ずっと独り身でしたね。
晩年、芝公園に転がり込んだ、わずかひと月半ほどを除き、5年ばかり、毎日、神田の駅前に、サラ金会社のPR看板をかついで立つという、いわゆるサンドイッチマンを生業(なりわい)にしたのです。
芝公園の最寄りの、港区は愛宕警察署に出向き、いかにも刑事〝面(づら)〟をしている、ベテラン警察官(小説の中の鷹来(たかぎ))に伴われつつ、署内の地下にあった遺体安置所にて、私は親父の亡骸(なきがら)と対面しました。そのくだりは、小説の中では【こう】です
★ ★ ★
「でも矢沢さんは幸せだよ。俺ね、あなたへの電話が通じた時に、もしや、この人、引き取りに来ないんじゃないかと思ってね。ま、長年、この仕事をしている男の、勘ってやつなんだが……。あなたの顔を拝めてさ、正直ホッとしたんだよ。これで仏さんも救われる」
「ちょっと待って下さい」
恭一は顔をやや引きつらせた。
鷹来は、おや? という表情をする。
「勝手にホッとされても困ります。俺、親父の遺体の確認をしろ、と言われたからやって来たまでで、引き取る気なんてさらさらありませんよ。親父もそれは承知の上です。もしのたれ死んだら、線香一本だけは手向けてやる。かりにも血縁である親子の社交辞令として、それだけは約束する。でもあとは知らない。俺の知ったこっちゃない」
おのずと声が大きくなるのを、鷹来は聞いているのかいないのか、遺体袋のジッパーを一体ずつ開けていき、五体目で「あー、これだこれだ」とつぶやいた。
彼にうながされ、恭一は袋の中を覗き込んだ。思った以上に肌の色がほの白く、頬に触れてみた途端に手を離してしまった。たまげるほど冷たかったからだ。白髪交じりの太いへの字眉に、眉間のやや上の、大きめのホクロ。見飽きたはずの一寛の顔だ。
ほんのひと月前、別れ間際に恭一の小説の下手さ加減を説いた口元は、今、何かをやり遂げた後のごとく、誇らしげに引き締まって見える。あの台詞は遺言代わりだったのか。
「お父上に間違いないかい?」
「ええ、たしかに。……ついにこの世とオサラバしやがった。でも親父にとっては、きっと本望ですよ、こういう死に方は」
鷹来は、あからさまにギョッとした顔になった。
「女房や子供たちを放りだし、稼いだ金はみごとなくらい手前のためだけに使いまくった人生ですから、今更、思い残すこともないでしょう。若い頃からすでに世捨て人で、浮遊が口癖でしたけど、要するに人間の営みのすべてが信じられない。仕事の仲間、友人、恋人、夫婦、親子……。すべてから逃げていたいだけ。そんなに嫌なら、脳天気に子供なんか作らなきゃいいんだ」
恭一は一寛の額を平手で叩いた。
パチン!! 静まり返っていた空間に、異様に音が響き渡った。
★ ★ ★
身内の恥はこのくらいにして──、肝心の昭和歌謡の話題に移ります。
長谷川きよしという、盲目のアーチストをご存知でしょうか? 流行歌手という意味では、大ヒットとまでは行かなくても、中ヒットぐらいは飛ばした、昭和歌謡史に燦然と輝く名曲『別れのサンバ』(昭和44年7月25日発売/作詞&作曲:長谷川清志)!!
と、もう1曲、
オリジナルは、直木賞作家の野坂昭如の楽曲でしたが、さほど当たらず……、数年後、長谷川がカバーしたことで、全国的に認知された『黒の舟唄』(昭和50年10月25日発売/作詞:能吉利人/作曲:桜井順)があります。
私は、特に5番の歌詞が気に入ってましてね。
♪~おまえと俺との あいだには
深くて暗い 河がある
それでも やっぱり 逢いたくて
エンヤコラ 今夜も 舟を出す
ROW&ROW ROW&ROW
振り返るな ROW
振り返るな ROW~♪
親父は広告屋の端くれでしたから、各レコード会社から新発売されるレコードの【視聴版】が、けっこうな数、わが家で埃をかぶっていました。野坂バージョンと長谷川バージョン、およそアレンジの異なる2つの『黒の舟歌』を、生意気にも私は、小学生の分際で聴きまくっていたものです。(→後編へ続く)
![]() 勝沼紳一 Shinichi Katsunuma
勝沼紳一 Shinichi Katsunuma

古典落語と昭和歌謡を愛し、月イチで『昭和歌謡を愛する会』を主催する文筆家。官能作家【花園乱】として著書多数。現在、某学習塾で文章指導の講師。