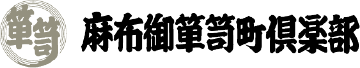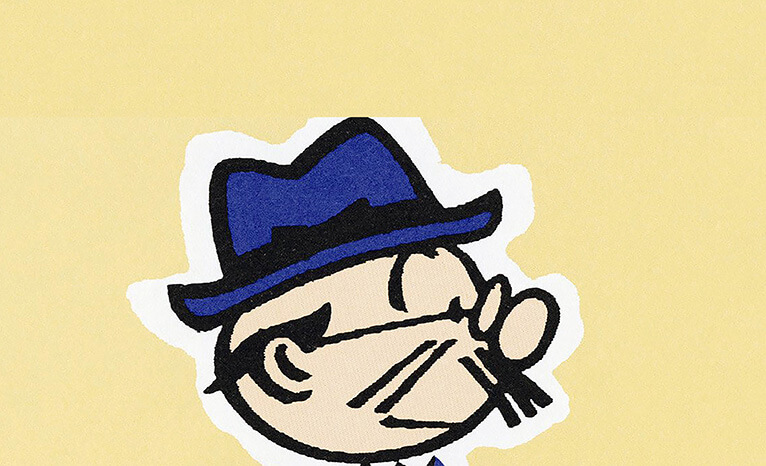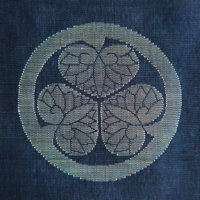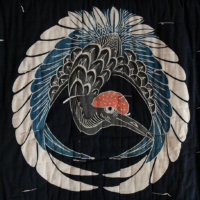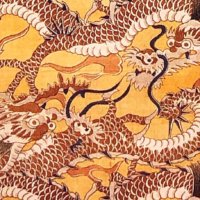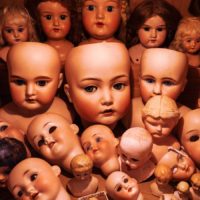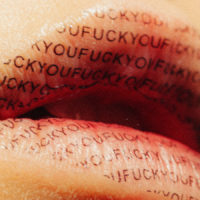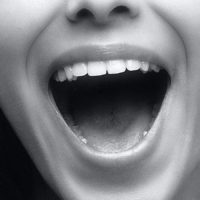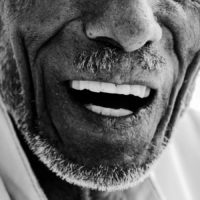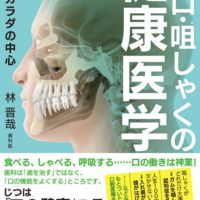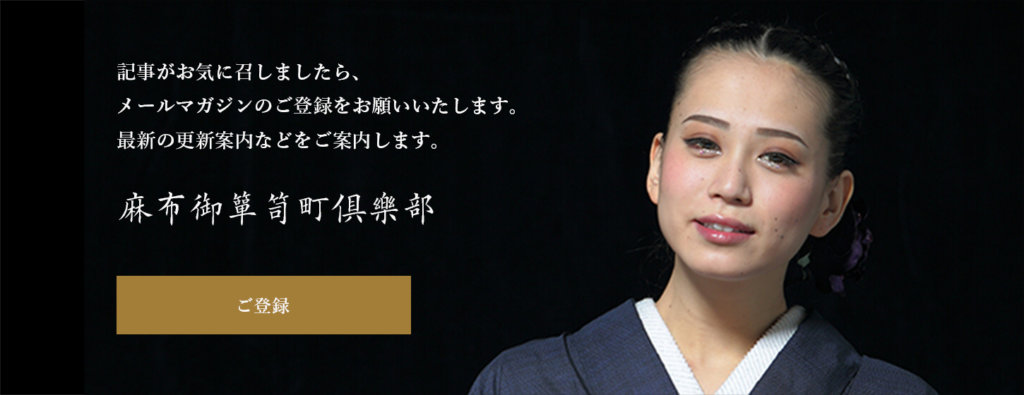平成三十年 雨水
使われちゃあ、いませんか

機心
使われちゃあ、いませんか
この数年〈機心〉という言葉が、頻繁に頭に浮かぶ。
特に、地下鉄や電車に乗った時に多い。
原因はスマートフォンにある。
今やスマートフォンの中には、メールも、音楽も、ゲームも、漫画も、ネットも、テレビとカメラとビデオそしてSNSときて、定期券を含めたカード機能まで入ってしまった。
そのうちパスポート情報まで入って、海外旅行にもスマートフォン一台で行ける時代が来てしまうのではないかと、いささか怖くもある。
さて、電車である。
車両の中はスマートフォンの嵐である。
車内はさほど混んではいないのに、こちらの眼前に突きつけるように、一心不乱に画面を見ている馬鹿(敢えて言う)も多い。
どうしてくれようと、睨みつけたその視線さえ感じない輩のなんと多いことか。
さらに、彼らが必死に覗き込んでいる画面が、ゲームであったり漫画であったりする可能性が高いことが、私の怒りの沸点を高くする。
これが子供や若いお嬢さんならば許すくらいの、ほんの少しの度量は私にもある。
しかし、これがどう見ても人の親である世代の、いい歳をした中年親爺であると、怒りを通り越して疑問を感じてしまう。
彼らに[恥]という概念はないのか、外国人に比して日本人の行儀の良さは、恥意識の高さからくるものだと言われるが、これはどうしたものか。
確かに、これだけの機能を持ったスマートフォンは、通勤通学の車内の暇つぶしにはもってこいである。
もちろん遊びだけではなく、仕事で使用している人も多いだろう。
だがどう見ても私にはスマートフォンという機械に操られているように映る。

機械あれば機心あり
機心とは、『荘子』の天地篇に〈有機械者、必有機事。有機事者、必有機心〉「機械あれば必ず機事あり、機事あれば必ず機心あり」とある。
ある時、孔子の弟子の子貢が田園地帯を歩いていると、一人の年老いた農夫が畑に水を撒いていた。
その農夫は、川から手作業で水を汲むと、土手を上り降りして、一杯一杯行きつ戻りつ水を撒いている。それは大変な重労働であった。
子貢は、テコの原理を利用した〝はねつるべ〟という便利な仕掛けがあり、それを使えば、もっと楽に畑に水を撒くことができるので、その作り方を教えてあげようと、年老いた農夫に言った。
農夫、答えて曰く「私も〝はねつるべ〟を知らぬ訳ではない。それを使えば楽になることはわかる。しかしそれでは、手ずから畑に一杯一杯水を与える精神性が損なわれる。私にとっては、楽をすることよりも、作物に対峙する精神性の方が大切であるので無用である」
老夫にとって、機械に頼る心〝機心〟は、堕落としか映らないのであった。
※はねつるべ/柱で支えた横木の一端に石を付け,他端に取り付けた釣瓶を石の重みではね上げ,水を汲み上げるもの。『大辞林』三省堂
現代を省みるに、〝はねつるべ〟という原始的な道具どころか、便利、楽をする道具に溢れかえっている。
それで人は幸せになったのか。
その象徴的な風景が、電車内に溢れるスマートフォンの嵐であるような気がしてならない。
休日の電車で目の前の席に父親、母親、男の子の親子3人連れが座っていた。
左に座る父親は体を左に傾けスマホでテレビを見ている。真ん中に座る子供はまっすぐにスマホに向かい一心不乱にゲームをやっている。右に座る母親はこれまた右に体を傾けてスマホで必死にメールを打っていた。
これが休日にどこかに向かう車内での親子の風景である。
皆さんも同じような光景を目にすることが多いのではないだろうか。
この風景に違和感を覚えるのは私だけなのであろうか、自分の子供時代を振り返ると、親子であろうが全く一緒に過ごす時間というのは案外短いものである。
この時間に親子が違いにそっぽを向いてスマホを見ていたという記憶は、先々子供にとってどう影響するのであろうか_余計なお節介であるが心配である。
それでは、お前はどうなのかと問われると、残念ながら同類である。
編集の仕事の関係上、締切や校了が近づくと、スマートフォンに寄稿者の原稿や校正、デザイナーからの変更レイアウト、印刷会社からの色校正調整などのメールやPDFが転送されてくる。移動中にこれらの確認や作業をすることも多い。
では、いつでもどこでも対応ができるようになり、雑誌や制作物の品質が上がったかといえば、〝否〟である。
いつでもどこでも対応できるという安心感が緊張感を失い、それこそ老夫の云う〝精神性〟を損ねているような気がする。
時間にルーズな知人は、携帯の普及によって、余計に遅刻をするようになった。
いつでも、遅れると連絡さえすれば許されると思っているのだ。
やはり〝精神性〟の問題である。
しかし、通勤の電車の中で我が『麻布御簞笥町倶樂部』を読んでくださるのは、とってもありがたい。
などと、想いを巡らせながらi.phoneをかざして改札を出た_あっ!