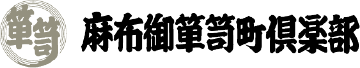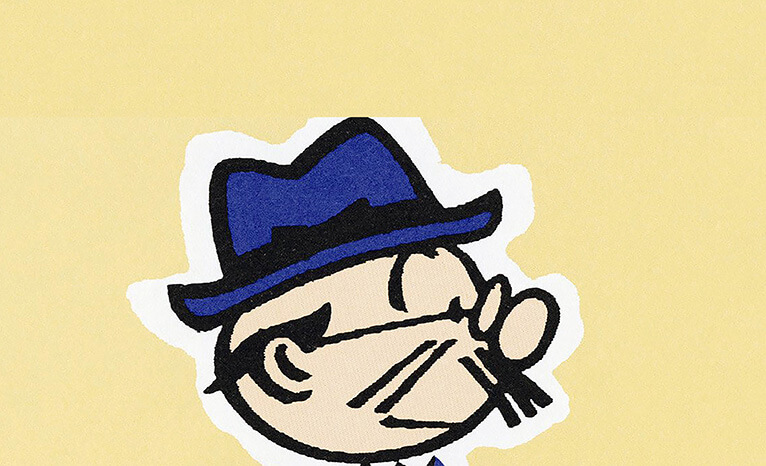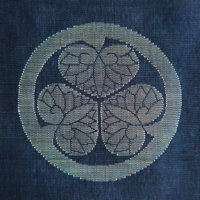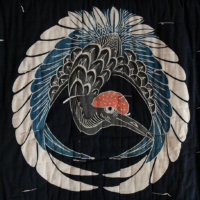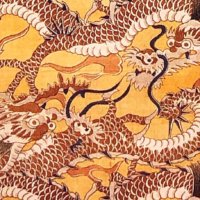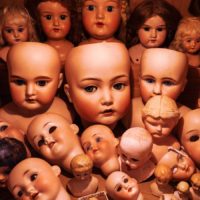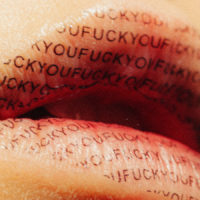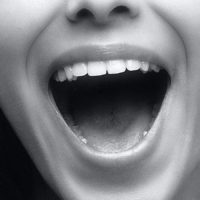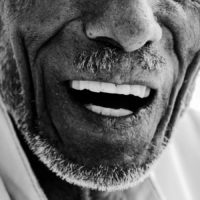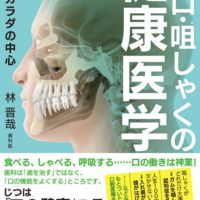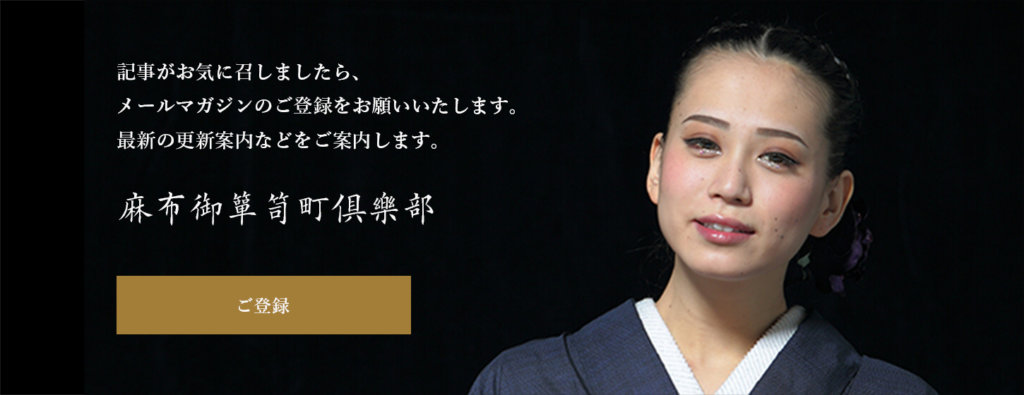令和元年 大暑
本物の力

玉露のいただき方
大暑
大暑_大いに蒸し暑く、大いに曇っている
令和元年七月前半(一日から十五日まで)の東京の日照時間が観測史上過去最低だという。
観測によればこの期間の日照時間の一日平均が30分に満たなかったという。
こうなると農作物への影響が気になるところである。
最近は料理関係のサイトを配信〈https://chefpartners.jp/〉しているため、食材への関心が否が応にも高くなり、作物への影響が大いにある天候にも気を配るようになった。
隠居親爺の身であればこそ、残り少ない食事に滋養多き作物をいただきたい。
親爺に〈不味いものを食っている暇〉はないのである。
決して高級食材をいただきたいというのではない。
近郊の旬のものを旬の時期にちゃんといただきたいだけなのである。
そう、我々の子供の頃のように—
魚売り
昭和30年代の初めの頃である。
九州の片田舎の私の郷里では、早朝に魚市場からおばさんがリヤカーを引いて魚を売りに来た。
おばさんの引くリヤカーの後ろは、木製の水槽になっていて、その中に売り物の生きた魚が泳いでいた。
祖母が魚を選ぶと、おばさんは手早く水槽からその魚を取り上げ、刺身か、煮るのか、焼くのかを祖母に尋ね、それに合わせて、手早くその場で捌いてくれた。
幼い私にとって、リヤカーの水槽は水族館であり、おばさんの包丁さばきは魅力的なショーだった。
毎朝、おばさんのリヤカーが待ち遠しかった思い出がある。
今のように、一般家庭が外食をすることは滅多になく、もともと田舎に洋食レストランなぞあろうわけもなく、店も物も少なかったが、今振り返ると、なんと贅沢な食生活であったかと思う。
お盆や正月、祝事などの宴席では、大皿に盛られた刺身がいつも卓の中央に置かれていた。
しかし、やがて毎度毎度出される大皿の刺身に、酒を吞めるわけでもない子供の私は、幾分辟易としてた時期もあった。
それが大学で上京して東京の刺身を食べ、そのあまりの不味さに、いかに自分がこれまで旨い刺身を食べていたのかを初めて知った。
河豚もそうである。
郷里からは下関が近かったので、河豚は当たり前のように魚屋にあり、魚売りのおばさんや魚屋は、当然のように河豚を捌く、私の郷里では商売として魚を扱うものが河豚を捌けないようでは話にならなかった。
我が家の食卓でも、冬場は十日に一度ほどのペースで〝てっちり〟が上ったし、河豚刺しも他の刺身同様に供された。
河豚もまた、上京して初めて高級料理であること、ほとんど一般家庭では食べられないことを知った。
何も、私の家庭が特別裕福であったわけではない。
大体の家庭が同じようなものだったと思う。
もちろん東京でも高いお金を払えば、旨い刺身も、河豚も食べることができる。
しかし、一般家庭の家計で賄える金額で、新鮮な旬の魚が上ったかつての田舎の食卓と、どちらが社会として豊かであるかは明らかである。
玉露のいただき方
五月二日の「八十八夜の別れ霜」から3ヶ月近く経ち、ようやく我が家も、令和の新茶〈煎茶・抹茶・玉露〉を求めることができた。
毎年、背伸びをして求める新茶は、宇治の三星園上林三入本店のものである。
同店の歴史は古く、現在の店主の方は二十一代目にあたる。
店名にある開祖〝上林三入〟は千利休に茶葉を提供した〈御茶師〉であり、江戸時代には将軍家や諸大名にも納めたという。
何しろ茶畑の地図記号が、同店の屋号と商標である三星から取られたという逸話があるほどである。
宇治から江戸の将軍家に収める際の「茶壷道中」が同店からも出立したらしい。
わらべ歌の「ずいずいずっころばし」は、この茶壺道中の様子を
—茶壺に追われて戸っぴんしゃん—茶壺道中が来たので戸をぴしゃりと閉めて外に出ない
—抜けたら、どんどこしょ—通り抜けたら表に出てなんでもして遊べる
と、歌っている。
茶壺道中は、百人から二百人、多い時には千人もが連なるの道中であったと云い。
何か不手際があれば責任ある者は切腹、切り捨て御免の無礼打ちもあったというほどのもので、街道の人々にとっては恐ろしいものだった様子が、わらべ歌では歌われている。
それほどまでして運ばれたお茶、将軍家や諸大名が好んだものと同じものをいただいていると思うと、なんだか楽しくなる。
もっとも、我が家で求めるものは、同店の商品の中でも高級なランクのものではないので、気分だけであるか。
10年以上前に、三星園上林三入本店を取材した際に、第二十一代店主に〝玉露のいただき方〟を教えていただいたことがある。
〝玉露〟とは「覆い茶」に分類されるもので、これは茶葉に覆いを被せて育てる被覆栽培で出来たお茶を云う。
玉露の覆いは、二から三週間と期間が長く、高級品は、茶畑に作った棚に藁などをかぶせて覆うという伝統栽培でつくられる。
茶摘みも機械ではなく、良い芽だけを選別して手で摘まれるため、より良質になるという。
さて、いただき方だが
まず玉露の茶葉を10グラムほど入れた専用の小さな急須に氷水を注ぎ、10分ほど待って出てくる数滴をいただく。
まさに〝玉の露〟という銘の意味を知る思いがする。
この方法で三度ほど楽しめるという。
ご亭主曰く、低い温度の水であれば、お茶の苦みの成分であるタンニンが出ないため甘くなるのだという。
この甘味を十分楽しんだら、四回目からは少し温度を上げていただく。
ほんのりとした苦みを感じるが、味はまろやかだ。
六回目からは六〇度ほどの〝湯冷まし〟でじっくりいただく。
ここで、三つの水の温度ごとに違った味を噛みしめる。
ある程度の品質の普通の煎茶でも、この氷水、のち湯冷ましで淹れれば、苦味のないまろやかな味を楽しむことができる。
しかし、普通の茶葉はここまでで捨てる事になるが〝玉露〟の場合、出し切った茶葉は、〝おひたし〟や〝かき揚げ〟にして食べると良いと、ご亭主は仰った。
良いものは、それを真っ当に扱いさえすれば、結果、安いという良い例である。
世の中には紛い物も多い。
「玉露風」と表記するべきものを、「玉露」と銘した商品のなんと多いことか。
早く、安くを追い求めて量産される「食品添加物だらけの見栄えだけは良い食品」を卒業して、不格好でも旬の食材を旬の時期に、旬の地域で食する〝地産地消〟を、掛け声だけではなく、皆が意識して家庭料理を楽しめば、自然に食料自給率も上がると思うのだが、如何であろうか。