令和六年 雨水
首をやるやる
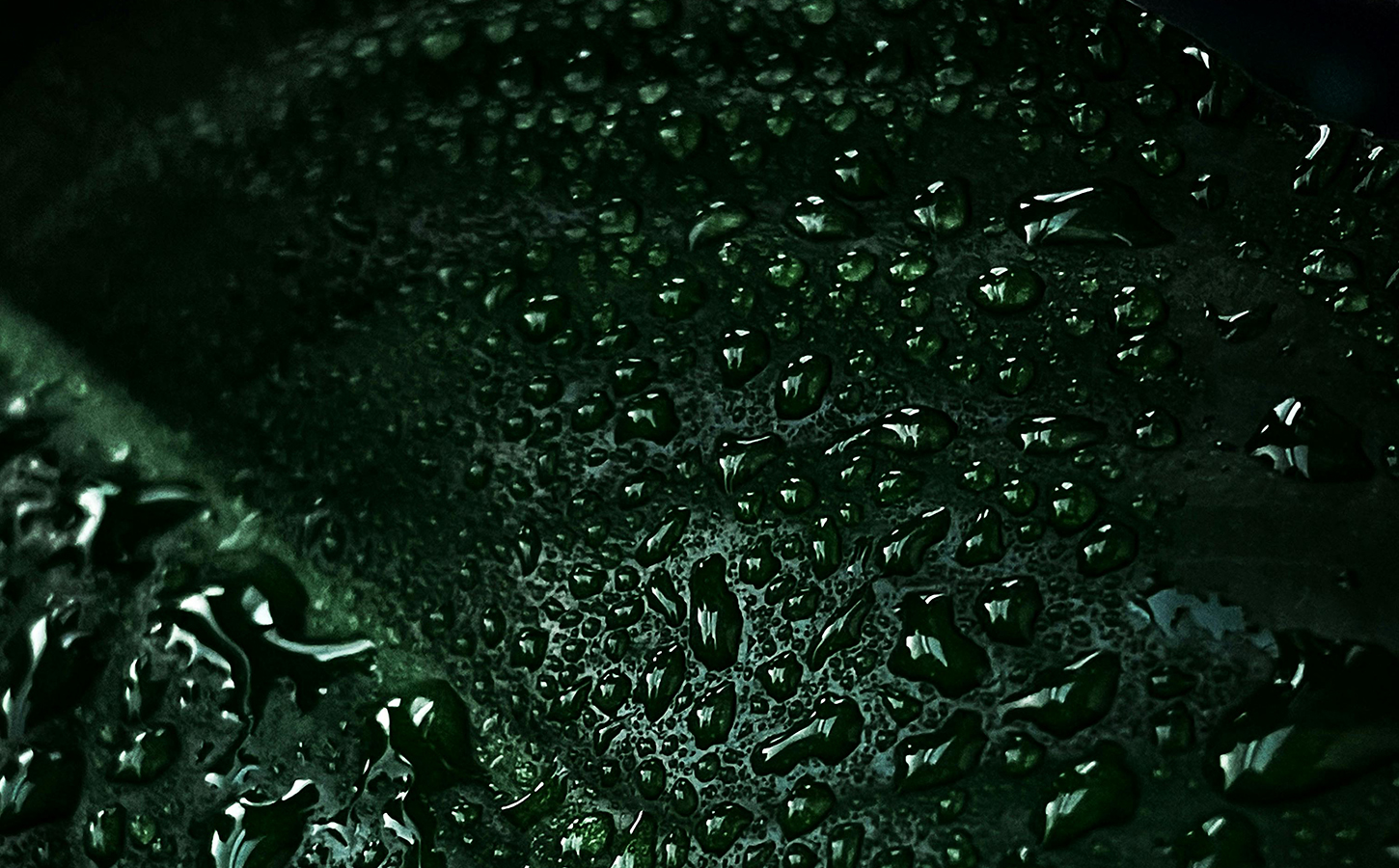
カタキだ
春の雪
雨水_山野の雪解けが雪汁となって田畑を潤す時。農家では年の新たな農作業の始まりとなる時期である。
藍染の材料となる〝蒅(すくも)作り〟の始まりでもあり、徳島県の吉野川沿岸では蓼藍の種が撒かれる〝藍撒き〟が行なわれる。
初春とは言え、まだまだ冷え込む日が続く。『小寒』のコラムで—冷んやりとして空気が澄んでいた。こんな「大気冴ゆ」とでも呼ぶような、冴え冴えと澄み切った朝には居間のベランダから富士山が綺麗に見える。—と書いたが、立春以降の、こんな寒さの日を〝冴返る〟と呼ぶのだそうだ。
春の季語でもあり、夏目漱石に「真っ青な 木賊(とくさ)の色や 冴返る」という一句がある。
また立春を過ぎて降る雪を〝春の雪〟と呼ぶ。特に関東地方・東京に多く降るが、〝春の雪〟はどうも天気が乱れるだけでなく、後世に残る動乱も引き起こすようだ。
1860年(安政7年)3月3日(新暦3月24日)。季節外れの春の大雪の日。脱藩した水戸藩士17名と薩摩藩士1名の計18名が、〝安政の大獄〟を主導した彦根藩主で大老の井伊直弼を江戸城桜田門にて襲撃し暗殺する。いわゆる『桜田門外の変』が起こっている。
その約80年後の1936年(昭和11年)2月26日から2月29日にかけて、陸軍の皇道派青年将校たちが起こしたクーデター未遂事件『二・二六事件』が発生した。
この〝春の雪〟を伴った椿事は、どちらも日本の歴史に遺り続けるであろう。たまたま舞台がそうなったのか、どちらも志を持った青年たちが、実権を握る幕府・政府の要人に対し命がけで引き起こした事件であることが、この二つの春の雪の日の事変を我々の頭に刻む。
などとボンヤリ考えていたら、そういえば萩原健一・ショーケンが『二・二六事件』を描いた映画『226』で事件の首謀者・野中四郎大尉を演じていたなと想い起した。ショーケンが亡くなったのが2019年の3月、享年68歳。うーん、来年私もその68歳となる。
そ、そんな、売春みたいなこと
先日、二日続けて千葉市川の知人宅に行く用事があった。拙宅からは片道1時間半、往復3時間がかかる。この無聊の時間を過ごすために未読の文庫本を持って出た。
本は、深沢七郎の『書かなければよかったのに日記』。1960年に発表した作品『風流夢譚/中央公論』が原因で右翼団体が殺傷事件を起こしたため深沢は三年間ほど休筆して各地を放浪した。本には、その前後の期間に書き溜めた日記風のものが収められている。
タイトルは日記となっているが、エッセイのようなものや短編小説風なものもあり、飽きることがなかった。読み進めていくと後半の部分に「首をやるやる日記」という章があった。この文章の内容が、今、騒がれている漫画を原作として制作されたテレビドラマの問題について作家・原作者の思いというものを、よく表していると思うので長いが抜粋を転載する。
深沢七郎「首をやるやる日記」/抜粋
—さて、僕は思うんだけど小説を脚本にして映画にすることなどはとんでもないことの様な気がする。映画の原作を書く人はそれ専門の人が創作でやる以外にはないと思う。私はデヴュー作「楢山節考」が映画化されるときまった時はとても嬉しかった。初めてなのでなんとなく嬉しかったのだ。そうしてあの作品は木下恵介先生が熱を入れていろいろな方面にも好成績だった。それで、私自身は映画化に対しては充分なのである。だから、もうボクの他の小説は映画にならなくてもいいと思う。それだけ私は満足感に浸ることが出来たのだった。
さて、僕ばかりではなく他の作家の先生方も私と同じことを考えていられると思うけど小説が映画化されることは決して原作料が欲しいという商品的な考えではないと思う。小説が映画化された方がいいと思っているのは出版社だと思う。それは小説の宣伝になるからだ。実際、映画化されればその小説は確かに売れ行きがいいのである。それで、著者と出版社は協同組合の様なものだと言われているので著者は自分の小説が映画化されるときは努力しなければ申しわけがないことになってしまうのである。
もともと文章の味で書いたものを他の味で出すことは邪道だと思うのだから、「そ、そんな、売春みたいなことはよせばいいのに」と作家はみんな腹の中では思っていながらやっぱり出版社に同調してしまうハメに落ちてしまうのである。そうして、(なんて、ツマラナイことだろう)と思いながら撮影のセットやロケーションに出かけて行って、「いい映画が出来るらしいですね」と演芸欄の新聞社の人に口から出まかせの吹聴をしてしまうハメにおちいってしまうのである。
映画会社の人達は儲かるように儲かるようにと努力するのだ。が、ホントは映画会社などツブれてしまえばいいのだとボクは思っている。そんなことは失礼だから言わないけどなぜツブれればいいと思うかと言うと映画は作家のカタキだと僕は思うのである。なぜカタキかと言うと、だいたい小説を書く時には映画にならない様にならない様にと思いながら小説を書くのである。書いているうちに映画の場面みたいになりそうになると(避けよう〳〵)と努力するのである。なぜそうしなければならないのかと言うと小説の味というものはそういうものだから仕方がないのである。
—中略—
〈日本〉教育テレビ〈現・テレビ朝日〉の第二制作の田中亮吉さんから電話がきた。「あの、東京のプリンスたちを、一時間ぐらいのテレビドラマにしたいのだが」と言われてドキッとした。
—中略—
テレビもラジオも映画と同じ様に小説のカタキなのである。
—中略—
竹森編集長さん〈中央公論社〉は「脚本を見てからきめましょう」ということになった。脚本は出来たが竹森編集長さんの所へは届けられずにお稽古の通知を知らされてその時原作の契約書に判を押してくれと言われてボクは判を押してそのあとで竹森編集長さんにそのことを話すと竹森編集長さんも呆れ返ってしまった。(この世の中はどういうことになるのかな、自分の思うこととは反対に、反対になってしまう)とボクも舌を巻いてしまった。
〈調べると『東京のプリンスたち』は1959年(昭和34年)12月10日 木曜日 の20:00 – 21:00で放送されていた〉
深沢七郎は、処女作の『楢山節考』を木下恵介監督が映画化したことには、喜び感謝するが、基本的には小説は文章の味というものがあり、それが映画・映像の味とは違って相容れないものと考えている。そして、小説を書く上では、映画の場面のようにならないように気をつけていると。あまつさえ、映画・テレビ・ラジオは作家のカタキであり、映画会社などツブレてしまえと書く。
深沢七郎は作家デビューする前は、日劇にも出演したことのあるギタリストだったため、ショービジネスや芸能の世界は他の作家よりも理解していたはずであり、その彼の思いがこれであれば、他の作家が感じた葛藤はこれ以上であろうと想像できる。もちろん深沢七郎ほど過激ではなかろうが、大筋では同様なのではあるまいか。
深沢作品が映画化されたのは、木下恵介監督『楢山節考/1958年』『笛吹川/1960年』。市川崑監督『東北の神武たち/1957年』今村昌平監督『楢山節考/1983年』の4本だけであり、テレビドラマは前出の『東京のプリンスたち』のみである。
木下恵介監督の『楢山節考』は原作の世界観に忠実であり、深沢も述べているように満足した出来上がりで、今村昌平監督の『楢山節考』は『東北の神武たち』と物語が合体された作品であるが、深沢の文章の味を踏襲した作りとなっているように思われる。大体において、小説の原作が映画化されたものを見るとがっかりさせられることが多いが、この二作品に関しては、満足のいく出来上がりとなっている。
ところで、この頃騒がれているテレビドラマの件であるが、漫画作品の原作者はドラマ化に際し、原作者の意図を充分汲むよう要望、契約書にも記したにも関わらず、それが反故にされたため、度々脚本の変更を要請、しまいには最終話を含む2話分の脚本を自身で書きドラマは終了。しかし、この経由などがSNSなどで拡散し炎上。不幸にして(定かではないが)これを苦にした原作者が自死してしまった、と報道から私は理解している。
原作者は、深沢が書くように(この世の中はどういうことになるのかな、自分の思うこととは反対に、反対になってしまう)と途方に暮れ絶望してしまったのではなかろうか。
ドラマ制作の「日本テレビ」、原作漫画の発行元「小学館」、これにドラマの「脚本家」の対応に非難が集中している。
深沢が書いているように、出版社は本を売らんがために映像化を推進し、テレビ局は番組作りのためには原作者など軽視する。出版社とテレビ局は大手企業であり、作家と脚本家は個人である。一目瞭然の力関係で個人は弱い。しかし、何もないところから小説や漫画を作り出す作業は生半ではなくシンドいものだ。この作業が軽視され、あたかも商品として右から左に動かして儲ける輩の権力が大きいのはなぜだろう。これに対して深沢は「映画もテレビもラジオもカタキだ」と断じ、「そ、そんな、売春みたいなことはよせばいいのに」と悲しみ、この文章のタイトルに「首をやるやる」と題した。
出版社とテレビ局に全くの努力と技術がないとは言わぬが、作家を蔑ろにするほどのものはないと考える。漫画を原作とするドラマ制作は、小説を原作としたものよりずっと簡単だと私は思っている。小説は人によってそこから感じる世界観が違ってくる可能があるが、漫画の場合はストーリーに加え漫画・絵という絵コンテがすでにあるのである。この世界観を原作者と脚本家が共有すれば済む話である。しかし、今回の場合も含め原作者と脚本家が実際にあって意見を交換することは稀であるという。
深沢の『東京のプリンスたち』のように、作家も出版局の編集者も知らぬうちに脚本が上がり、その脚本内容を原作者が確認もできず稽古の段階で知らされ契約させられるという呆れ返る手法が、このドラマの放送期1959年のテレビの黎明期から行なわれてきたとすれば、テレビ局というものの厚顔無恥な正体がここにある。
テレビというものが生まれてからわずか70年、文化となる前に消滅する運命なのはこの正体にあるのだろう。
次はネットかな。
編緝子_秋山徹


















































































































































