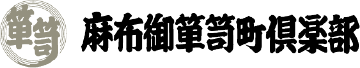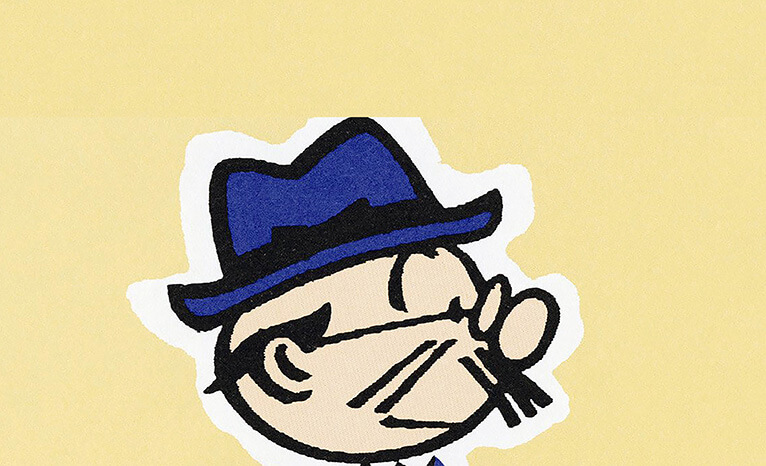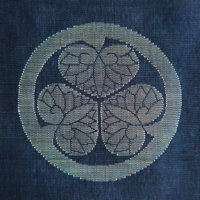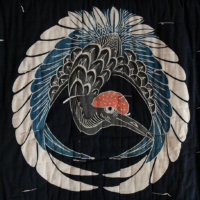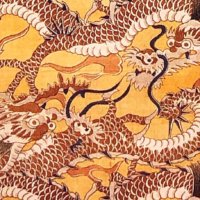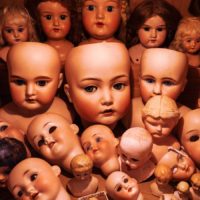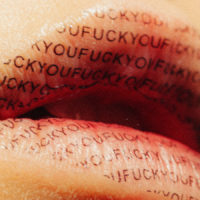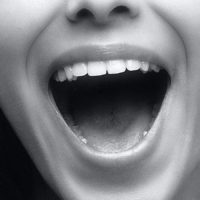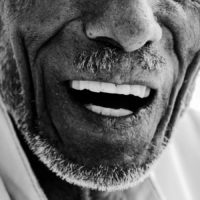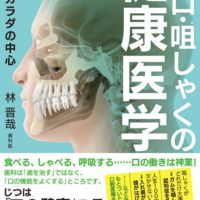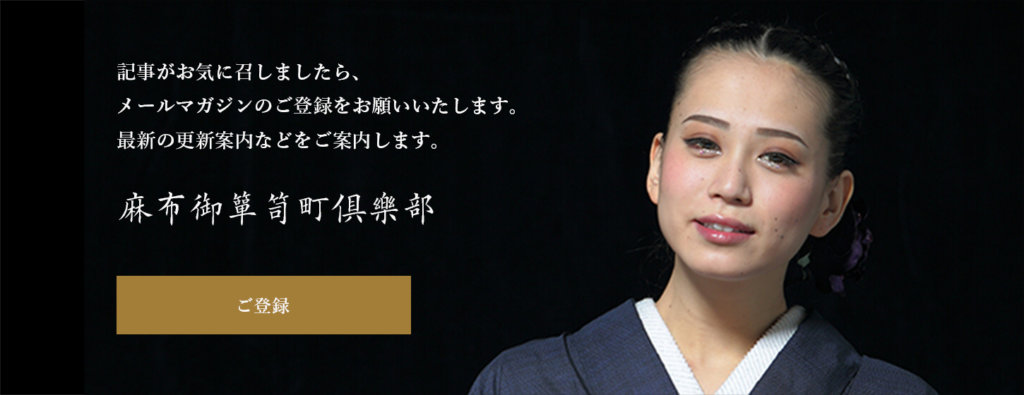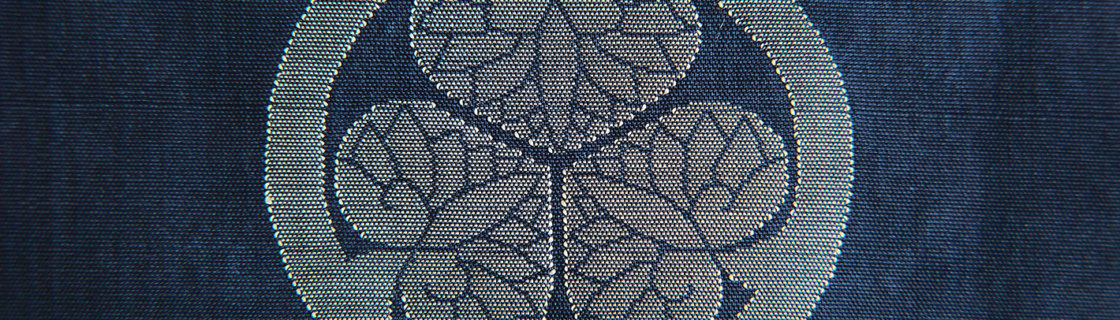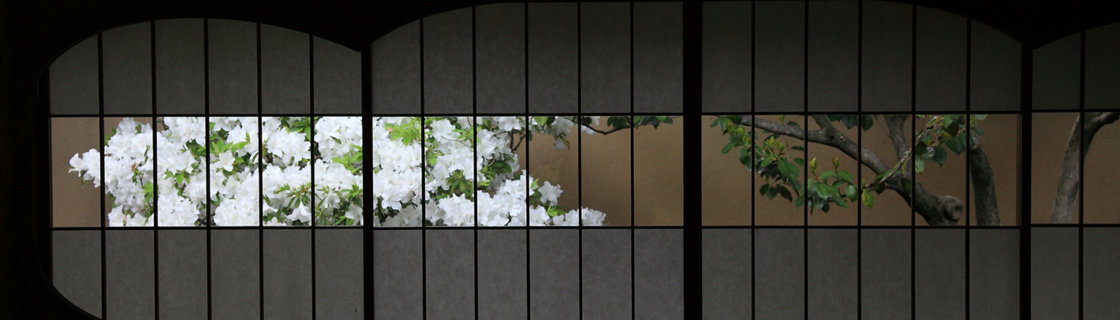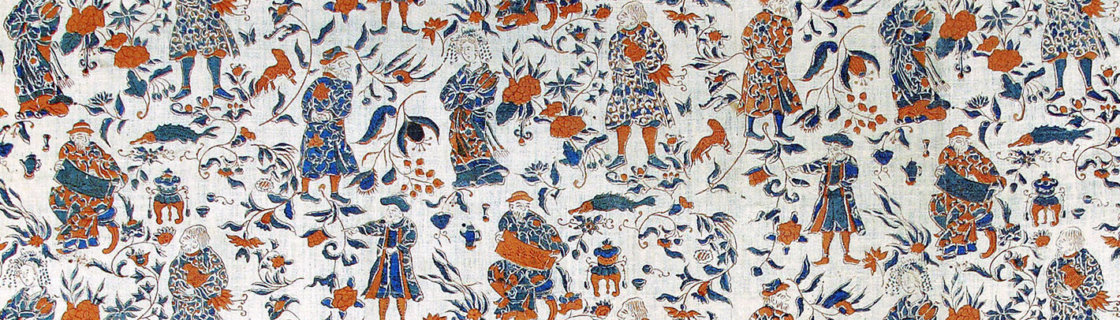北原ミレイ

昭和歌謡_其の三十七
2つの〝才〟に翻弄されて
『懺悔の値打ちもない』と『石狩挽歌』
なかにし礼と阿久悠
昭和歌謡の長い歴史の中で、超ビッグ・ヒットを飛ばした作詞家は数多くいますけれど、今年が13周忌になる阿久悠と、現在、癌で闘病中のなかにし礼くらい、才能の資質や作風はもちろん、歌詞に書かれる日本語の選択からして、まるで異なる2人も、他に例を見ないんじゃないですかね。
〝そこ〟には、生まれ育った環境の差異が大きく関わってくるわけですが、詳細はここでは省きます。あくまで〝ざっくり〟と分別してしまうと、兵庫県出身、明治大学の文学部を出て、広告会社に勤務した阿久と、満州に生まれ、幼少期、北海道や青森でいろいろ苦労をしつつ、思春期以降は東京で過ごし、立教大学でフランス文学を学んだ、なかにし……。
CMプランナーとして、常に宣伝効果を第一義とし、「売れるためなら、まず何をすべきか?」のポリシーを、作詞の創作活動にも踏襲した阿久、一方、学生時代からシャンソンの訳詞の〝バイト〟で稼ぎまくり、それぞれの楽曲のメロディに〝乗る〟ドンピシャリ的確な日本語の選択と、七五調(五七調)のリズムに、絶妙のセンスを発揮する、なかにし……。
この2人が晴れて売れっ子の作詞家になれば、紡ぎ出す歌詞の内容や〝台詞回し〟に、大きな差が出るのも、はなはだ当然の帰結ではないでしょうか。
以下は、あくまでワタクシの勝手かつ乱暴な〝分析〟ですので、それはご容赦願いたいのですが、2人の作風を比べますと、歌詞に描かんとするストーリーが、常に「ドキュメンタリー系」に傾く阿久悠と、「ドラマチック系」に傾くなかにし……。そうなるように感じます。
たとえば、ちょいと前のコラムに採り上げました、『別れの朝』(1971年10月25日発売/作曲:ウド・ユルゲンス)というビッグ・ヒットを飛ばした、ペドロ&カプリシャスには、あと2つ、看板ソングの『ジョニーへの伝言』(1973年3月10日発売/作曲:都倉俊一)と『五番街のマリーへ』(1973年10月25日発売/作曲:都倉俊一)がありまして、『別れの朝』の歌詞(厳密には訳詞)が、なかにしの作品。『ジョニーへの伝言』が、阿久の作品です。
『別れの朝』
♪~別れの朝ふたりは さめた紅茶のみほし
さようならのくちづけ わらいながら交わした
(中略)
言わないでなぐさめは 涙をさそうから
触れないで この指に 心が乱れるから
やがて汽車は出てゆき 一人残る私は
ちぎれるほど手をふる あなたの目を見ていた~♪
★ ★ ★
『ジョニーへの伝言』
♪~ジョニーが来たなら伝えてよ 2時間待ってたと
割と元気よく出て行ったよと お酒のついでに話してよ
友達ならそこのところ うまく伝えて
今度のバスで行く 西へも東へも
気がつけば さびしげな町ね この町は
(中略)
サイは投げられた もう出かけるわ 私は私の道を行く
友達ならそこのところ うまく伝えて~♪
いかがでしょう? こればかりは、個人的な印象としか言いようがないのですが、同じ〝恋仲〟だった男女の別れをモチーフにしつつ、まるで往年のフランス映画の1シーンのごとく、情感豊かなラブロマンスが描かれる『別れの朝』に引き換え、『ジョニーへの伝言』の方は、恋人と別れた女性に、直撃インタビューした際の、ズバリ率直な発言を聴かされている風に……私は感じました。
断っておきますが、どちらの【才】が優れているか否か? とかナントカ、そういう話をしたいわけではありません。明らかに歌詞を書かんとする際の、クリエーターの【作風】に、大きな違いがある!! ことを知っていただきたいだけです。
北原ミレイ2019
昭和歌謡ファンの間では、もちろん「有名歌手」ですが、世間一般的に、忘れられてしまった感の強い歌手に、北原ミレイがいます。彼女こそ、デビュー時に阿久悠、数年後になかにし礼、著しく異なった2つの【才】に翻弄されたことで、大輪の花を咲かせた人物と言えるでしょう。
愛知県豊川市出身、幼い頃からプロ歌手になりたかった彼女は、高校卒業後に上京し、ナイトクラブのステージに立ちながら、ジャズやカンツォーネの歌唱法を、本格的に学びます。ナイトクラブでの熱唱ぶりに、水原弘が惚れ込み、阿久悠に紹介されたことをきっかけに、1970年「ざんげの値打ちもない」(作曲:村井邦彦)でデビューします。
1970年という年は、音楽業界的には「ビッグアイドル誕生前夜」と呼ばれていましてね。翌71年にデビューするのが、南沙織、天地真理、小柳ルミ子の3人だと記せば、多くは語らなくても、おわかりになると思いますが、
その前年の同期デビューとなると、可愛い〝キャピキャピ〟系のアイドル歌手はただ1人、岡崎友紀のみ。あとは、にしきのあきら(現・錦野旦)、平山三紀、尾崎紀世彦、松崎しげる、安倍律子(現在・里葎子)、寺尾聰(ソロとして)、安岡力也(ソロとして)……。名前を列記するだけで噴き出したくなるほど、よくもまぁ、いかにも癖のありげな、大人びた雰囲気の〝新人〟ばかり、揃ったものです。
この仲間に、北原ミレイも加わらざるを得なくなります。当時、彼女だって22歳ですから、じゅうぶんに〝大人〟として互角の勝負も挑めるはずです。
ですが……、それが事実だとしても、晴れがましいデビュー曲のタイトルが『ざんげの値打ちもない』(1970年10月発売/作曲:村井邦彦)というのは、どうなんでしょう?せめてもう少し、新人らしいフレッシュな息吹が感じられる、そんなタイトルの楽曲を、本人が「唄いたい!!」と切望しても、決してわがままな要求ではないと思われます。
作詞を担当した阿久悠から、歌詞を受け取った彼女は、真っ先に「ざんげって、教会とかでよくやる、……あの懺悔ですか?」と訊いたそうです。阿久がどう答えて、北原ミレイを煙に巻いたのかは知りませんが、歌詞を読み進めるにつけ、彼女の気持ちは、デビューに向けてのウキウキと弾む感覚から、加速度的に遠のいて行ったようですね。
♪~あれはニ月の寒い夜 やっと十四になった頃
窓にちらちら雪が降り 部屋はひえびえ暗かった
愛と云うのじゃないけれど 私は抱かれてみたかった~♪
なんてべったりと澱んだ歌詞でしょう。まだ14歳のみそらで、寒くて暗くて、ジメジメと黴(かび)っぽい部屋の隅で、少しも愛してない野郎に処女を捧げちゃう。理由は「抱かれてみたかった」から……。ううむ、まるっきり救いというものがない!! しみったれた風な辛気臭さも同居しています。よくもまぁ、こんなミモフタモナイ歌詞を、新人歌手に提供しますよねぇ。阿久悠って男は、やっぱり只者じゃあない(褒めてませんよ~)。
でも、1番の歌詞はまだネンネです。3番で19歳になった彼女は、胸中のルサンチマンのすべてを一気に吐き出さんとして、凶行に及びます。
♪~あれは八月 暑い夜 すねて十九を越えた頃
細いナイフを光らせて にくい男を待っていた
愛と云うのじゃないけれど 私は捨てられ つらかった~♪
嗚呼、殺しちゃいましたよ、相手の男を。そして4番の歌詞で、刑務所に服役するのですが、その部分の歌詞だけ、NHKはもちろん民放各局でも放送禁止となり、以来「幻の4番」と言われています。
♪~あれは何月 風の夜 とうに二十歳も過ぎた頃
鉄の格子の空を見て 月の姿がさみしくて
愛と云うのじゃないけれど 私は誰かがほしかった~♪
昭和歌謡のヒット曲の中で、囚人を主人公にした楽曲は『ざんげの値打ちもない』だけです。松尾和子が唄う『再会』は、似たテイストですが、主人公が罪を犯したわけではなく、刑務所に入った恋人の、一刻も早い釈放を望む、その胸の内を描いた楽曲ですから、テーマの根本が異なります。
さて、罪を償ってシャバに出てきた彼女は、おそらくはXmasの夜でしょうか、街のドンチャン騒ぎをよそに、あちこちの教会で多くの信者が祈りを捧げる……そのタイミングに、私も誰かにひっそり、自分の過去を聴いてもらいたかった、というのがラスト5番の歌詞です。
♪~そしてこうして暗い夜 年の忘れた今日のこと
街にゆらゆら灯りつき みんな祈りをするときに
ざんげの値打ちもないけれど 私は話してみたかった~♪
先に私は、阿久悠の作風を「ドキュメンタリー系」と決めつけましたが、この楽曲は、その真骨頂!! まさしく〝その通り〟──じゃありません?
私は1980年代半ばから15年ほど、膨大な数のブルセラ女子高生たちの取材を行ってきました。中学を卒業する頃に、すでに1人で店に使用済みパンツやブルマー、唾や小便まで売りまくり、〝そういうもの〟が商売になることを知るや、次第にキスも売り、ペッティングも売り、早い話が売春でボロ儲けをしても、少しも感情が動かない。決して悪びれることなく、「べつに減るもんじゃねぇし」とうそぶく女の子たちの【その後】を、リアルに見せつけられ続けてきましたから、この歌詞の女の顛末が、決して作り話に思えないんですね。
「若気の至り」などという、通り一遍の言葉では、200%取り返しがつかない現実というものが、この世にはあるのだと、思いっきり悟らされました。でも、そういう末路をたどる女の、最初の1歩は、まず間違いなく、全員が全員、ほんのちょっとした〝トッポイ(死語ですかね?)〟好奇心から始まるんですね。おそらくこの理屈に、昭和も令和も、時代の隔たりなど関係ないでしょう。
まぁ、その方向の話は、ひとまず置いておくことにして……、北原ミレイの歌手としての人生は、この先、それこそ「ドキュメンタリー系」としては、どう進んでいくか? 歌詞の内容はともかく、……いや、ひょっとして歌詞が〝こう〟だったからこそ、みごと『ざんげの値打ちもない』は大ヒットします。デビュー曲で、オリコンチャートが最高14位、レコードの売上枚数、約20万枚というのは、お見事です。
同時に、この歌詞を唄いこなせたことで、阿久悠以外のクリエーターも、彼女の歌唱力に着目します。デビュー5年後、シングル8枚目となる楽曲『石狩挽歌』(1975年6月25日発売/作曲:浜圭介)は、初めて、なかにし礼が作詞を担当しましたが、これがまた、デビュー曲とは異なる意味で、きわめて歌唱が難しい、まさに「ドラマチック系」な歌詞内容でした。
♪~海猫(ごめ)が鳴くからニシンが来ると
赤い筒袖(つっぽ)のやん衆が騒ぐ
雪に埋もれた番屋の隅で わたしゃ夜通し 飯を炊く
あれからニシンはどこへ行ったやら 破れた網は問い刺し網か
今じゃ浜辺で オンボロロ オンボロボロロ~
沖を通るは 笠戸丸 わたしゃ涙で ニシン曇りの空を見る~♪
なかにしはこの歌詞で、同年の「日本作詞大賞」の作品賞に輝きますが、改めてこうして記してみると、確かに流行歌にしておくのが、もったいないほど上質な日本語の表現でありまして、七五調のリズムといい、言葉の選択といい、純粋な〝ポエム〟として、高校の現国の教科書に載せたいくらいです。
特に私が感服するのは、サビの部分にインサートさせた、絶妙なオノマトペ(擬音)ですね。かつて隆盛を誇ったニシン漁もすっかり寂れ、今じゃ、その痕跡すら残らないほどに番屋もボロボロに朽ち果てた。その様子を「オンボロボロロ~」とは、よく描いたものです。言葉の【音】としても【意味】としても、リスナーの耳に、意識に、ダイレクトに響きますからね。
挽歌は、英語のエレジーと同種で「死者を悼む歌」のことです。しばらくスランプに苦しんでいた、なかにしにとって、作詞家生活で初めて、自分の身の上を私小説風のテーマとして選び、「ドラマチック系」に仕上げた勝負作が、ズバリ『石狩挽歌』です。1フレーズ、1フレーズ、歌詞に、なかにしの情念が漲(みなぎ)っています。
歌唱する彼女も、大変だったでしょう。
「まず歌詞の意味が、ところどころ、まったく解らないんですよ~(笑)。海猫を【ごめ】って言うのか。漁師が身につけるあの格好は、筒袖【つっぽ】って言うのか。いちいち、なかにし先生が教えてくれて、初めて『あー、なるほど!!』って。歌詞の内容が解らないと、気持ちを込めて唄えませんから、レコーディングに入るまでに、けっこう時間がかかりました。そんな曲は、私も長く歌手をやってますが、後にも先にも『石狩挽歌』だけですね」
北原ミレイは、後年、何かのインタビューに応えて、そう語っていました。
歌詞に描かれた1人の女性の生き方を、デビュー曲の『ざんげの値打ちもない』では「ドキュメンタリー系」に、『石狩挽歌』では「ドラマチック系」に、唄い分けねばなりません。決して簡単な〝技〟ではありません。
美空ひばりや、近頃また、ベスト盤のアルバムが飛ぶように売れているらしい、ちあきなおみは、この〝技〟にメチャメチャ長けた唄い手ですが、どっこい北原ミレイも、昭和歌謡史に遺る、とびっきり優れた唄い手であることを、この機会に、改めて多くの皆さんに知っていただきたいです。
![]() 勝沼紳一 Shinichi Katsunuma
勝沼紳一 Shinichi Katsunuma

古典落語と昭和歌謡を愛し、月イチで『昭和歌謡を愛する会』を主催する文筆家。官能作家【花園乱】として著書多数。現在、某学習塾で文章指導の講師。