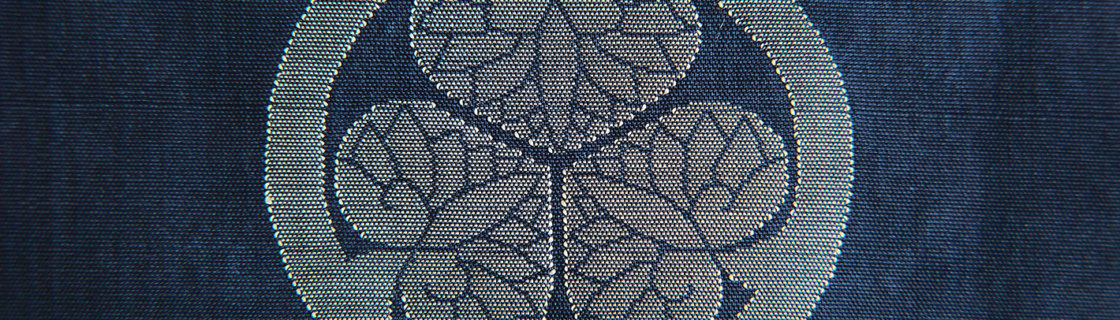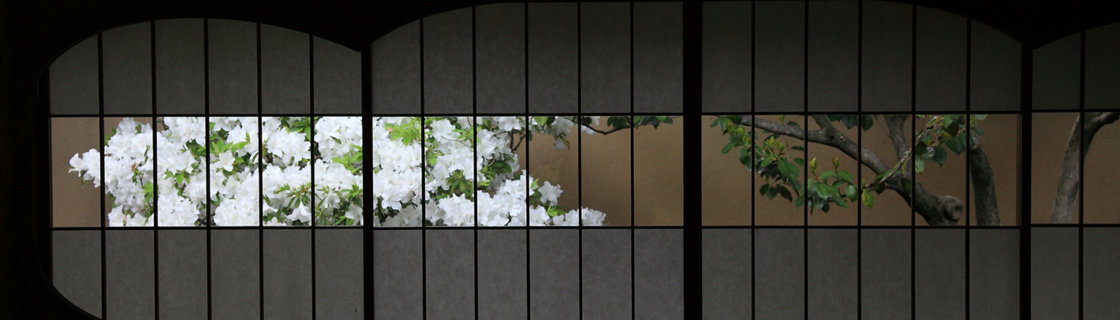萩原健一 前編

昭和歌謡_其の三十八
旧盆の入りを前に ショーケンを悼む
私が住まう高崎の日中の気温は35度……を、さらに超えて38度。野外の炎天下、ぎんぎらのオテントウサマの熱をダイレクトに浴びる地面は、おそらく50度以上に〝燃えて〟いるはずです。
毎朝、テレビ各局の気象予報士たちは、異口同音に視聴者に命じます。「大変危険ですから、屋外での運動は取りやめてください」と。
そんな危険な環境の中、来年のちょうど今頃、世界中の選りすぐりのマラソンランナーがメダルを賭けて、42.195kmの距離を走る!! 大丈夫なのでしょうか? いや、大丈夫のはずがない!! 走行中、熱中症で倒れる選手は続出するでしょう。ひょっとして死人も出るかもしれません。いや、きっと出るでしょう。オソロシイ……。
死んじゃうといえば、ショーケンこと萩原健一が亡くなって、4ヶ月とちょっと経ちました。享年68というのは、まっとうな人間の最期とすりゃあ、確かに若すぎますけれど、相手は〝あの〟ショーケンです。若い頃にさんざん悪さ(ヤンチャ)しまくった、あのツケ、このツケの累積ぶりを想えば、皮肉抜きに、むしろ68年間も生きて来られた奇跡とやらに、感謝すべきかもしれません。
ほどなく彼にとって初めてのお盆がやって来ます。彼岸から、ふらりと俗世へ舞い降りてくるタイミングに、ちょいとばっかり、あくまで形だけの追悼の意を込めまして、私なりの「墓碑銘」を記したいと思います。
私は現在、56歳ですので、正直、彼がGS(グループサウンズ)の超人気バンド『ザ・テンプターズ』のボーカルだった頃の活躍ぶりは、ほぼ語る資格がありません。
彼が役者に転向し、私の小学生時代、日本テレビ系のドラマ『太陽にほえろ!』のマカロニ刑事として、TV画面に登場した時、幼いなりに、ショーケンの演技に強く惹かれた記憶があります。
すぐにマカロニ刑事は、特に若い女性の視聴者の人気を得て、番組としても〝それ〟を売りにするようになると、その生温(ぬる)さに安住するのを毛嫌い、みずから監督やプロデューサーに進言し、番組内で、惜しまれつつ殉職する道を望みます。しかも「なるべく刑事らしくない死に様、はなはだ情けなくてみっともない死に様、を俺は演じたい!!」……と。
もちろん、ドラマ制作の裏側に、そのような実話が隠されていたのを知ったのは、ずっと後です。いや正直言いますと、つい最近です。
ショーケンの死後、動画サイトのYOU-TUBEに、彼に因んだ映像が立て続けにアップされていましてね。『太陽にほえろ!』の主要キャストだった、〝チョウさん〟こと下川辰平が、ショーケンに〝みっともない死に様〟の例として、戦時中の特攻兵士の逸話を持ち出し、
「『天皇陛下、万歳!!』と叫んで敵機に突っ込んだ、というのは、都合の良い後付けの理屈であって、実際には、覚悟も決まらず、自分の母親に命乞いしながら死んで行った兵士も多かったらしいよ」
と話してやったそうで。ショーケンはその〝実話〟にえらく刺激を受け、さっそく組み立てた演技プランが、〝あの〟有名な殉職シーンになりました。夜中に道端で、立ち小便をし終えたタイミングに、暴漢に刺され、「お母ちゃん、暑っついなぁ~」とつぶやいて絶命する……。
傷だらけの天使
続いてショーケンが主役を演じた、同じく日本テレビ系のドラマ『傷だらけの天使』は、オンエア当時よりも、脚本の勉強を始めた頃の私が、やけに影響を受けた作品でした。
監督は深作欣二をはじめ、恩地日出夫、工藤栄一、神代辰巳ほか、脚本は市川森一をメインに、鎌田敏夫、永原秀一、柏原寛司ほか、という、現在の民放テレビドラマでは、絶対に「あり得ない!!」豪華過ぎるラインナップ。
市川森一が書いた、第7話『自動車泥棒にラブソングを』の脚本は、「――鳩が、糞をたれて、飛び立つ。」という、1行のト書きから物語が始まります。
このト書きの魅力について、大学に在学中、脚本指導の教授が語ってくれた〝分析〟が、今でも強く印象に残っておりまして。
「ドラマが放映された1974年当時、日本人の多くは、すでに先の大戦で手痛く負けたことなど、すっかり忘れたがごとく、平和と繁栄に溺れきっていた。でも、それはあくまで表層の薄っぺらい部分だけであり、巷のそこかしこに、軽薄な時代に取り残された、不器用な老若男女が存在する。『傷だらけの天使』は、一見、時代の申し子的チャラチャラした若造2人を主人公にしつつ、じつは【そうではなく】、彼らは彼らなりに、時代に抗い、傷つき、必死にもがきながら日々、生きている。そんなドラマ展開を予感させる、シナリオの冒頭が、「――鳩が、糞をたれて、飛び立つ。」だ。平和の象徴である鳩が、臭くて汚い糞をたれる。それはまさしく、70年代半ばの日本全体が、経済成長と国民繁栄の名の下、溜め込みすぎた、鼻をつまみたくなるほど臭い、消化不良の糞である」
それまでテレビドラマの脚本といえば、倉本聰と山田太一がベストで、市川森一のことは、ほとんど関心がありませんでした。『傷だらけの天使』のメインライターだったことも、知りませんでした。教授の〝分析〟に、大いにたまげてしまった私は、脚本のト書きは【こう】書かねばならぬ、という教訓を仕入れたのと同時に、
『傷だらけの天使』の最終回、ショーケン演じる修(おさむ)の舎弟分、水谷豊演じる享(あきら)が、〝たかが風邪〟をこじらせて死んでしまい、それを認めたくない修が、享の遺体を素っ裸にしてドラム缶風呂に入れ、享が大好きだったエロ本のピンナップを全身に貼り付けては、泣きながら、
「アキラ~、起きろよ!! 童貞のまま死ぬんじゃねぇよ。ちゃんと女とヤッてから死ねよ!!」
と叫びまくるシーンを、再放送によって、あらためて鑑賞し直してみて、嗚呼、まさしくこれが「鳩の糞の正体だな」……。鳥肌が立つほど切なく感じ入ったものでした。
後年、ショーケンはさまざまな事件を起こし、マスコミの報道では、上手い演技をする役者と言うよりも、犯罪者のごとく扱われるケースが多くなりましたよね。私が一番残念だったのは、2004年10月30日公開の映画『透光の樹』の、主演降板事件です。根岸吉太郎監督、田中陽造脚本、萩原健一&秋吉久美子のW主演だったのですが、撮影に入ったばかりの頃、ショーケンが秋吉に「暴行を加えた」ことから、「強制降板」させられ、それを不服とするショーケンが、ギャラを支払わないプロデューサーに対して「電話で恐喝した」……というのですが、
元はといやぁ、秋吉がイイ加減な仕事ぶりをショーケンに見せつけたのが、事の始まりだったのです。ああ見えてショーケンは、黒澤監督や勝新太郎、倉本聰ほか、昔気質の仕事ぶりをする凄腕のクリエーターに、鍛えられてきた役者です。
本読みやらリハーサルなど、きちんと「やるべきことをやる」のが役者の務めだと信じ切っているんですね。ところが時代が変わり、制作予算も減り、テレビドラマはもちろん、映画の現場でも、特に若手の監督の場合、「やるべきことをやる」流儀が、まったく通らなくなりました。
秋吉は、デビュー当時から顔見知りの【同士】だという、勝手な認識が、ショーケンの中に強くあったのでしょう。久しぶりに〝本編〟の現場、それも秋吉とW主演というので、彼のテンションはかなり盛り上がっていたはずです。せっかくだから、きっちり昔ながらの現場流儀で「やるべきことをやり」たかったショーケンと、そんなこと「もう時代錯誤よ!!」と鼻で笑う秋吉とで、確執があったのも事実でしょう。
昔はそういう状況になると、監督やプロデューサーが上手く仕切ったものだそうです。ところが根岸監督は、まったくそういうことに不向きなタイプで、苛立たしさがヒートアップしたショーケンは、怒りにまかせて「てめぇ、仕事を舐めてんじゃねぇ!!」と秋吉を怒鳴り散らし、つい秋吉に手を上げてしまった……。秋吉はわざとのように大声で叫び、「キャー、私、ショーケンに殺される!! 警察を呼んで~!!」と訴えたものだから、大事件に発展したのです。
この映画自体は、永島敏行を代役につけ、急きょ撮り直して、無事に公開されました。私も映画館で鑑賞しましたが、ハッキリ言って、ショーケンの代役は永島には荷が重すぎます。秋吉も、本音じゃショーケンと演りたかったはずで、永島との濡れ場は、少しもエロティックに感じられませんでしたね。
ショーケンは、若い頃の素行の悪さが災いし、加えて警察沙汰もたびたびだったため、世間の評価はほぼ「お騒がせ者」で確定し切ってしまった感がありますが、こと演技に関して【だけ】は、どんなベテランの役者よりも、よほど真面目に研究、習得し、その成果を忠実に撮影現場で「具現化させたい!!」がため、命がけの取り組みをしてきた〝事実〟があります。
その〝事実〟について、映画関係者や評論家連中は、とっくの昔に気付いていたようです。特に文芸評論家として著名であり、その独特の批評眼は、時に「作家を殺してしまう」ほど辛辣な、絓(すが)秀実が、経緯の詳細は不明ですが、じつに綿密な取材をショーケンに敢行しましてね。その膨大なデータを整理し、新書判に1冊、まとめ上げた本が、『日本映画[監督・俳優]論 ~黒澤明、神代辰巳、そして多くの名監督・名優たちの素顔~』(ワニブックスPLUS新書)です。
![]() 勝沼紳一 Shinichi Katsunuma
勝沼紳一 Shinichi Katsunuma

古典落語と昭和歌謡を愛し、月イチで『昭和歌謡を愛する会』を主催する文筆家。官能作家【花園乱】として著書多数。現在、某学習塾で文章指導の講師。