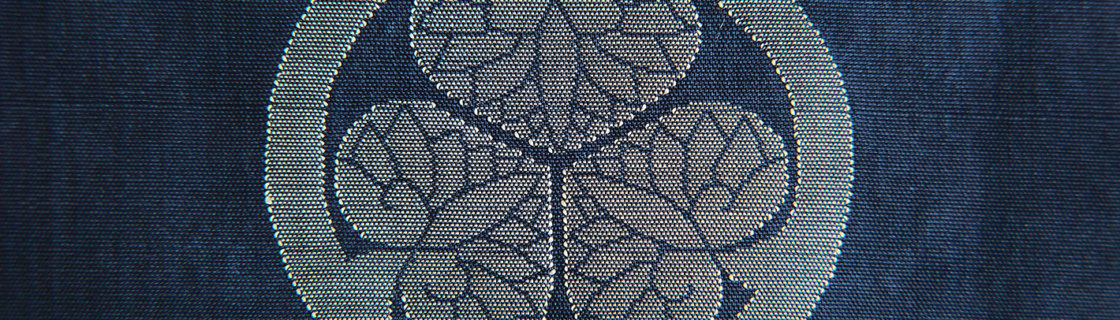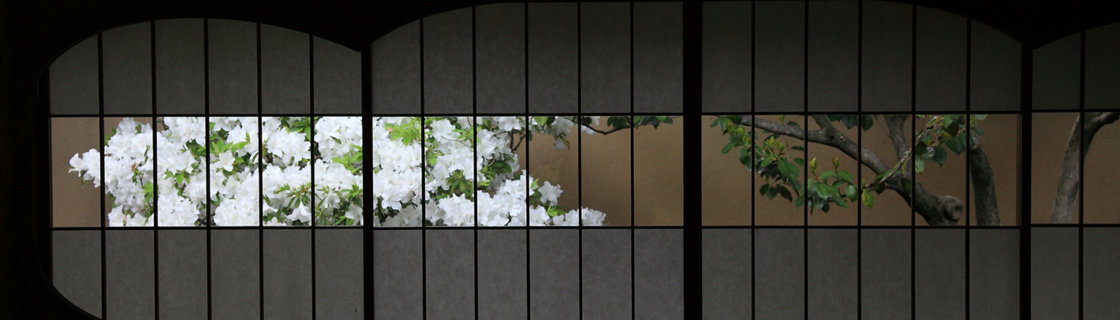藤圭子

昭和歌謡_其の二十二
圭子という名で
沢木耕太郎『流星ひとつ』
藤圭子が、自殺という不幸な最期を迎えてから、早くも5年以上の月日が流れたんですね。
死後ほどなくして、ノンフィクション作家の沢木耕太郎が、帯にわざわざ目立つ朱文字で「緊急刊行!」と銘打った、単行本『流星ひとつ』を出しました。
この本はじつに不思議な代物で、本来ならばウン十年前、藤圭子の全盛期に世に出なければならなかったインタビュー集だったのです。それを、「今さら、こんなタイミングに、どういう了見で出しやがった?」という大いなる疑問と、いささかならぬ憤りが、当時、私の自意識を猛烈に掻き回したものです。
もう1つ、けったいだったのは、全編、沢木と藤、ご両人の会話のみ、地の文は一切なし、という形式の書物だったこと……。担当編集者のアイデアだったようですが、刊行の時期が時期だけに、活字に変換されているとは言いながら、冒頭から延々と、膨大な数の、藤圭子の若かりし頃の〝肉声〟を読まされると、おのずと彼女のあの独特なハスキーボイスが蘇り、私自身、彼女とサシで会話している錯覚に陥りました。
私は学生時代から沢木耕太郎の〝文章〟のファンで、特に1979年に刊行された『地の漂流者たち』には強く惹かれました。アングラ演劇に青春を燃やす若者、ピンク映画の上映館に足を運ぶ若者、集団就職で零細工場に勤める若者、防衛大学に通う若者ほか、1970年代後半を生きる16~19歳ぐらいまでの〝無名の連中〟の日常を、沢木は常に「自分だったら、どうする?」という視点を忘れずに、彼らと共に笑い、共に泣き、時には共に寝泊まりしたり……その〝ありのまま〟を、情感込めて綴った1冊でした。
私がこの作品を愛読したのは大学に入ってからでしたが、1979年当時、私は高校2年生、登場人物たちとほぼ同年代であることに、不思議な縁(えにし)を感じておりました。それぞれの章に描かれる「青春」は、私の置かれる状況とまったく異なるものでしたけれど、でも何故か、彼らが沢木に吐き捨てる本音の1つ1つに、「うむ、俺もそうだ」と深く頷いている自分がいるんですね。
世の中は日増しにイケイケドンドン、脳天気な明るさだけが際立つような時代でしたけれど、そんな巷の〝空気〟を、あえて拒絶するような毎日を、登場人物たちはもちろん、じつは私も送っていたのです。
沢木耕太郎の作品の多くを、私は「私小説ノンフィクション」と名付けています。本来、ノンフォクション作家は、あくまで取材の対象者を客観的に捉えて文章を紡いでいくものですが、沢木はそうではなく、まず目の前の対象者に「ワタクシ」を投影させます。対象者の記憶および喜怒哀楽と、みずからの〝それ〟とを重ね合わせながら、真実に迫っていく――方法を取るのです。
『流星ひとつ』に収録されている、藤圭子へのロングインタビューは、ほとんど1979年の秋に行われたそうです。つまり『地の漂流者たち』が世に出た年に、沢木は、わざわざ人気絶頂の演歌歌手を、取材対象者に選んでいることになります。
藤圭子の最期が自殺だったこと、そして数ヶ月も経ずに『流星ひとつ』が〝緊急刊行!〟されたこと、この2つを無理やり重ね合わせると、ひょっとして沢木は、『地の漂流者たち』の登場人物の延長上に、藤圭子も捉えていたのではないか? そんな想いがリアルに膨らむのです。
藤圭子
藤圭子の両親は、ともに売れない浪曲師でした。三味線を弾きながら路上を徘徊し、声をかけてくれた座敷に上がっては芸を披露する。ついでに、女性の場合は体も売るという、いわゆる〝門付〟で生活を賄うような、そんな貧乏暮らしが幼い彼女の日常でした。
藤圭子の不幸は、派手な生き方など少しもしたくないにもかかわらず、家計を支えるため、高校進学を断念して流行歌手になったことでしょう。歌の上手さは、両親から譲り受けた才能として、地元でも有名だったようです。
15歳の時に、北海道は岩見沢で行われた雪まつりの「歌謡大会」のステージに立ち、見事な喉を披露する姿が、某作曲家の目に留まり、上京します。作詞家の石坂まさをを紹介され、マンツーマンのレッスンを経て、1969年9月25日に『新宿の女』でデビュー。いきなりレコードを88万枚も売り上げ、新人ながらスター歌手の仲間入りを果たしました。
さらに『女のブルース』(1970年2月5日発売/作詞:石坂まさを/作曲:猪俣公章)、『圭子の夢は夜ひらく』(1970年4月25日発売/作詞:石坂まさを/作曲:曽根幸明)、『命預けます』(1970年7月25日発売/作詞:石坂まさを/作曲:曽根幸明)……と、立て続けに大ヒットを飛ばします。
藤圭子は、当時まだ未成年です。北海道での貧乏暮らししか知らない田舎娘が、いきなり右も左もわからない大都会に連れて来られ、華やかな芸能界のど真ん中に引きずり出され、眩しいばかりのスポットライトを浴び続ける日常……。戸惑いばかりの毎日だったことを、沢木のインタビューの中で正直に告白しています。
私が藤圭子のことを、『地の漂流者たち』の登場人物の延長上に考えたいのも、以上のことが理由です。彼女は集団就職で上京した、数多くの若者たちの仲間だと決めつけても、まったくおかしくない境遇に置かれていたのです。
おまけに彼女の持ち歌のどれもが、暗く重たいテーマを扱った歌詞内容ばかりです。担当プロデューサーや所属事務所の方針として、「決して笑わない歌手」「怨念をまとった歌手」というキャラを演じさせられました。本人の元々の性格は、まるで逆だそうです。これも『流星ひとつ』を読んで、初めて知ったことです。
なにしろデビュー当時のキャッチフレーズは、「演歌の星を背負った宿命の少女!!」ですからね。本来は天真爛漫、笑うことが大好きなのに、それを厳しく封じられ、スター歌手で居続けるためには、♪~15、16、17と、あたしの人生 暗かった~♪ の歌詞通りの女として生きるしかなかったわけでしょう。これを〝宿命〟という一言で片付けてしまっては、あまりに彼女が可哀想な気もします。
ひょっとして人気絶頂期の頃から、自殺という最期が、藤圭子の自意識の中におぼろげながら浮かんでいたのではないか? そんな仮説すら浮かんできます。
『京都から博多へ』
そんな彼女が、1972年1月25日に発売した楽曲が、『京都から博多まで』(作曲:猪俣公章)です。それまで作詞を担当していた、演歌畑の売れっ子クリエーターではなく、「演歌は嫌いだ!!」と公言する阿久悠が、どういう経緯か、藤圭子に歌詞を提供することになったんですね。そして書き下ろした歌詞(3番)が、以下のとおりです。
♪~京都育ちが 博多に慣れて
可愛い訛りも いつしか消えた
ひとりしみじみ 不幸を感じ
ついてないわと云いながら
京都から博多まで あなたを追って
今日も逢えずに泣く女~♪
私は、藤圭子という歌手にまとわりつく、鬱陶しいほどの暗い印象が、どこか薄気味悪く感じまして、正直いうと、長いこと生理的に毛嫌いしてきました。私が主宰する『昭和歌謡を愛する会』でも、彼女の楽曲がどれほど大ヒットしようとも、頑なに無視してきました。
ころが藤圭子が亡くなり、『流星ひとつ』を一気に読み終えた時、どういう心境の変化でしょう。自分でもよく判らないのですが、急に聴いてみたくなったのです。彼女のデビュー曲から順に、看板ソングと思われる楽曲を十曲ばかり。
その中に、もちろん『京都から博多まで』も含まれておりまして、猪俣公章節ともいうべき、聴く者の情緒にしっとり絡みつく、味わい深いメロディはもちろんのこと、阿久悠が描く、特に3番の歌詞の内容に、強く惹かれました。
京都を北海道に換え、博多を東京に換えると、確かに貧乏だったけれど、純朴だったろう、幼い頃の彼女が、あれよあれよという間に、気付けば、東京の息苦しいほどの雑踏にも慣れ、すっかり一端(いっぱし)のスター歌手でござい、という顔で生きている。お金は儲かったから、欲しいモノは、とりあえず何でも買える。周囲のスタッフはちやほや、おだててもくれる。でも……。
「今の生活は幸せかい?」と訊かれて、すぐに「ええ、もちろんよ」とは答えられない何か? 今さら、口に出してもしょうがない何か? さまざまな愚痴や後悔が、藤圭子の胸中に溜まりに溜まっていき……。もはや、どうにもならなくなった時、衝動的に自宅マンションの13階から飛び降りてしまったのではないか? 薄笑みを浮かべ、かすれた声で「ついてないわ」とつぶやきながら。
阿久悠は、この楽曲のレコーデイングに際して、藤圭子に一切、演歌特有のコブシを回さないで唄うよう、厳しく注意したそうです。
「1フレーズ、1フレーズ、淡々と、台詞を吐き捨てるように唄うことで、この歌詞の主人公の心情が、より濃厚にリスナーに伝わる」
阿久悠のこの教えどおりの、〝つまらなそうに感じる〟彼女の歌唱と、情緒たっぷりなメロディとの、みごと過ぎる異化効果によって、結果的にこの楽曲は、他の藤圭子の持ち歌とは、いささか毛色が違う、昭和歌謡の名曲になりました。
多くのカラオケファンは、『圭子の夢は夜ひらく』に描かれる、♪~15 16 17と 私の人生暗かった~♪ の言葉に象徴される〝そういう〟イメージが、イコール藤圭子の実像と思われていらっしゃるかもしれません。
私もそれを、あえて否定はしませんが……、
私の、あくまで勝手な解釈からすると、根っから暗い人生が約束されていた訳でも何でもなくて、幼い頃の生活は確かに貧乏のどん底だったでしょうが、天性の無邪気さというか、ある意味、能天気っぽい朗らかさが、彼女の持ち味だったと思われます。
誰しも親は選べない。親の言いつけどおり、否も応もなく右なら右、左なら左、ただ従って生きてきて、歌手なんかになる気もなかったかもしれません。でも歌の上手さは親譲り、家計を支えるために、なかばプロの音楽関係者に連れ去られるがごとく、訳もわからぬうちに上京、そして気がつけばデビュー。
常に彼女の〝立ち位置〟は、周りの大人によって決められます。ワタシはそれに従うだけ。でも新たな環境への順応性だけは、意外とあるのでしょうね。これも両親ともに〝露天芸人〟の血でしょうか。オアシがもらえるならどこへでも出向き、ひとまず飯が喰える場所が、今宵の寝床になるという……。
京の訛りが「可愛い」と、恋仲の誰かに言われた過去も、博多暮らしに慣れると、綺麗さっぱり消えてしまう。「過ぎ去った過去に未練はない」と言わんばかりに。
『京都から博多まで』の歌詞から窺える心情吐露こそが、藤圭子の自分史そのものである、と私は考えます。
そして阿久悠が、そのあたりのことまで企んで、この歌詞を書いたのだとすると、やはり〝阿久悠オソルベシ!!〟ですね。
![]() 勝沼紳一 Shinichi Katsunuma
勝沼紳一 Shinichi Katsunuma

古典落語と昭和歌謡を愛し、月イチで『昭和歌謡を愛する会』を主催する文筆家。官能作家【花園乱】として著書多数。現在、某学習塾で文章指導の講師。