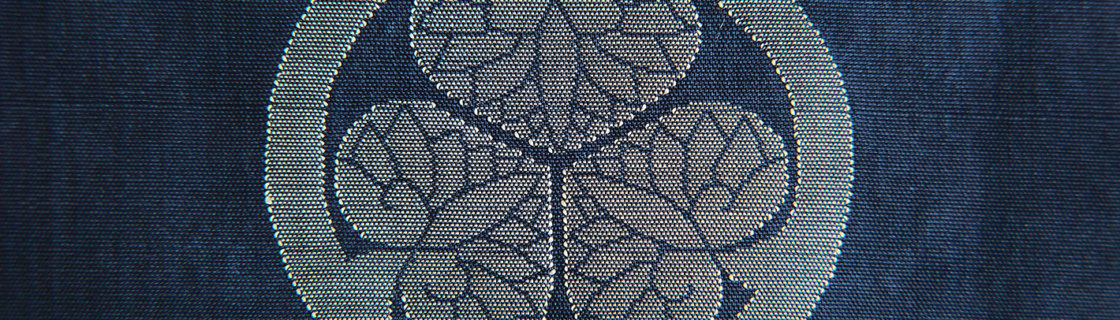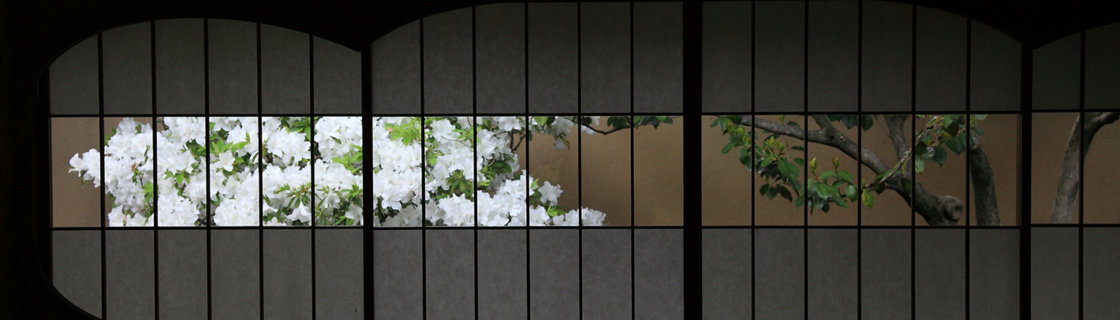夢魔の棲まう街 その九

フィレンツェ中央駅 Stazione Centrale
タクシーは、約束の時間を五分と遅れずにホテルに着いた。
イタリアでこの正確さは嬉しい。
だが運転手のパオロは、相も変わらず昨夜同様丸坊主で耳にピアス、無精髭の上にはペルソールの真っ黒なサングラスという形(な)りである。
このスタイルと時間に遅れぬ生真面目さのギャップが可笑しくて、思わず破顔ってしまったら、どうした、とサングラス越しに怪訝そうな顔を向けてきたので、いや、なんでもない、と返し、タクシーの後部座席に乗り込んだ。
ホテルまでの道に馴れていることと時間の正確さをかって、今日から明後日の昼までパオロのタクシーを貸し切ることにした。
これからの2日間は、これから中央駅に迎えに行く出版社の編集長と広告担当部長の二人をフィレンツェでフルアテンドしなければならない。
古都フィレンツェは歩きで十分な狭い街だが、大企業の無理を効かせるのが趣味のような連中だ、効率よく移動するのにタクシーを確保しておくに越したことはない。
編集者だライターだクリエイターだといっても、所詮は業務委託の下請けである。
メインクライアントには逆らえぬというのが、フリーランスとなって一等最初に学んだことであるが、今だに馴れない自分と馴れてはならぬと叱責する自分がいる。
郊外のホテルに二泊する羽目になったのも、もともと自分用に予約してあった街中のホテルの部屋を、急にピッティ・ウオーモを見たいと言い出した編集長に譲ったためであった。
部屋を譲るのはまだしも、同行してくる広告担当部長の部屋を、ピッティウオーモの期間にフィレンツェを訪れる者の常識として皆一年前から予約しているという状況の中、同じホテルでもう一部屋とるのには苦労した。
あらゆるツテを頼ってようやく部屋が確保できたのは、出発の二日前だった。
彼らにとっては、そんな苦労など気にも留まらない事柄であろうが、昨夜のミラノも、二日後のナポリも同様とあらば、こちらの気疲れも一層益すというものだ。
タクシーは、フィレンツェ中央駅へと発進し、昨夜暗闇の中を登った坂を下る。
道の両側の煉瓦塀の向こうに広がる深々と萌映る緑が心地よい。
昨夜は闇に隠れていた糸杉やオリーブの木々、なだらかな葡萄畑が浮き上がる緑の絨毯を形なす。
緑の中に点在する赤茶色したレンガの貴族の別荘が、精気を取り戻している。
坂を下りきって、ローマ門を抜け、チェントロ(街中)に入って中央駅のホームに着いたのは、ミラノ発の特急列車の到着予定時刻の20分前だった。
思えば、ミラノ、ボローニャ、フィレンツェ、ローマ、ナポリとイタリアを縦断するこの特急列車は、15年ほど前まではとても風情のある造りだった。
一等の車両は、6人掛けのマホガニー調の木製の個室に区切られ、椅子の上には扉付きの棚が設えてあって、各人の椅子の背もたれを手前に引けば、後ろからハンガー付きの一人用ワードローブが現れた。
いわゆるコンパートメント・タイプといわれる車両で、古い欧米の映画などで憧れていた車両に初めて自分が乗った時には、随分と昂奮したものだ。
貸し切りの個室ではないので、見知らぬイタリア人乗客と個室で一緒に過ごすこととなる。
イタリア人は初対面でも旧知の仲のように_私にはそう見える_会話を始めだす。
そんなことを思い出しながら、バールでカフェを飲っている間に、お目当の列車が15分遅れでホームに滑り込んできた。
列車に近づくと、編集長と部長は、ちょうど一等車から大きな旅行鞄と、ミラノのモンテ・ナポレオーネ通りに連なるハイファッション・ブランドの買物袋をいくつも抱えて降りて来るところだった。
思わず目を背けた先に、台車置き場があったので、台車に彼らの戦利品を乗せながら、よくミラノ駅で引ったくりに会わなかったな、と二人に聞こえぬように独り言ちた。
五十絡みの編集長は、焦げ茶の麻のテイラード・ジャケットに薄いブルーの麻のボタンダウンシャツを合わせ、白い綿のパンツにベルトは薄いベージュ色のクロコダイル、足元は薄茶のクロコダイルのスリッポンを素足に履いていた。
胸元に麻の白いポケットチーフを挿し、腕にはパネライのゴツイ時計をして、ご丁寧にパオロと同じペルソールの真っ黒なサングラスをかけていた。
彼の手がける雑誌のファッションページさながらのスタイルに、ゴルフ焼けした自慢の褐色の肌はそれなりにサマになっているが、惜しむらくは、身の丈と足の長さが少々足りなかった。
広告担当部長の方は、役職柄最先端のファッションというわけにもいかないのだろう、イタリア・ブランドのトレンドを取り入れた日本のブランドのグレイの麻のスーツに、白い麻のシャツに黒いストレートチップを履いていた。
面白くも可笑しくもなく、可もなく不可もない出で立ちだが、なぜか黒いベルトはベルサーチの派手なバックルのもので、これが悪目立ちしていた。
台車を押しながら編集長に、ミラノはどうでしたかと聞くと、鷹揚に頷いてから、一晩だからね、よくはわからないけど面白かったよ、買い物をし過ぎてしまったな、アッハッハと周りが振り向くほど大きな声で笑った。
私がパオロの車のトランクに二人の荷物を押し込むんでいるあいだ、パオロと編集長はお揃いのペルソールを指差しあって戯けていた。
アルノ河沿いの三ツ星ホテルにチェックインしてから、アカデミア美術館に向かった。まずは本物のダビデ像を見せてから、サン・ジョバンニ洗礼堂、ドゥオーモ(大聖堂)、バルジェッロ美術館を駆け足で廻り、シニョーリア広場にある老舗のバール〈リヴォワール〉の広場に面したテラス席に二人を座らせ、プロセッコを注文してから、私はひとりウフィッツィ美術館に向かった。
イタリア・ルネッサンスの至宝が散りばめられたウフィッツィ美術館は、フィレンツェに訪れた観光客が必ず訪れるべき場所である。
美術館に入るには、通常、長い入館待ちの列に1時間以上並ばなければならない。
しかし、翌日以降の入館であれば、専用の窓口に行けば予約ができる。
窓口に向かっていると、昨夜空港からタクシーの相乗りをした女性の二人組が、入館待ちの列を前に立ち尽くしていた。