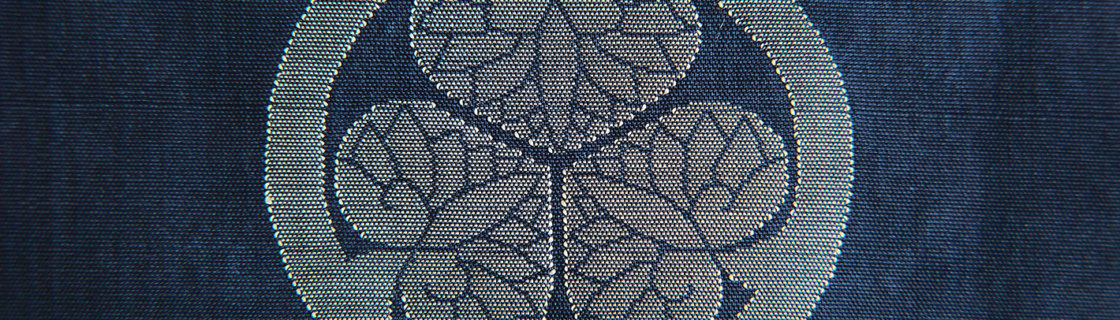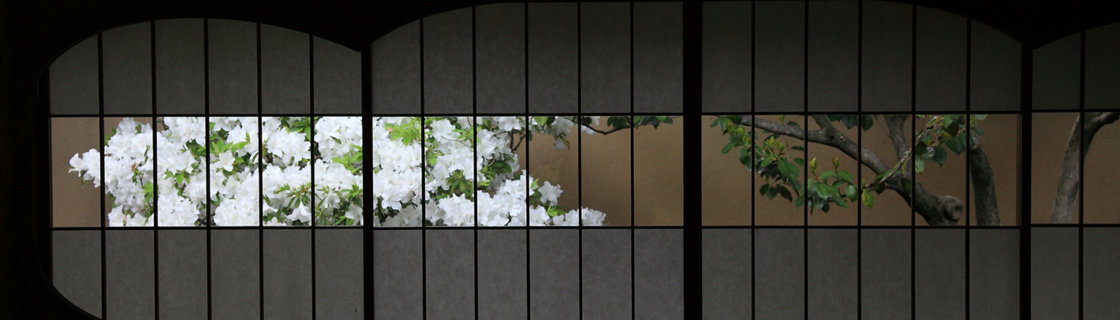夢魔の棲まう街 その十

チェントロ〈フィレンツェ市街〉 Centro
昨夜はどうも、どうしました、と後ろから彼女たちに声をかけた。
二人は振り向くと同時に、あーどうも、と声をあげた。
彼女らによると、フィレンツェ観光はまずウフイッツィ美術館からと朝一番に訪れたが、あまりの行列の長さに後に廻すことにして、再び来てみたら相変わらずの列の長さに唖然として立ち尽くしていたという。
彼女らに、明日以降の入館であれば予約が取れます、私もこれから明日の予約チケットを購入しに行くところなので一緒に行きましょう、とふたりを連れ立って予約カウンターに向かった。
カウンターでは、明日13:00の入館を予約してチケットを5枚購入した。
私には連れが二人いて、明日美術館を案内するので、一緒に回りませんかという提案に彼女たちが快く承知してくれたので、二人のチケット代もこちらで購入した。
自分たちの分はお支払いしますと何度も言われたが、明日、彼女たちが我々と一緒に回ってくれることの効果を思えば、本当に安いものだった。
美術館を出たところで、改めてお互いに名乗りあった。
すらりと背が高く、長い黒髪をラフに束ねてバレッタで留めているのが、大手商社に勤めている曜子で、細身のホワイトデニムにベージュのリザードのスリップオンを履き、薄いオレンジの麻のシャツの下に白い綿のタンクトップを着ていた。
同じくらいの背丈だが、濃い栗色の髪のボブスタイルで、大手のアパレルメーカーに勤める智美は、流行りのトッズの淡いブルーの皮のドライビング・シューズに白い綿のパンツ、淡いピンクの半袖のサマーニットという姿であった。
両者はともに肩に白と薄茶の皮の小振りのトートバックをかけていて、昨夜同様、旅に小慣れたスタイルだった。
二人は快活で屈託がなく、どこかしら生まれの良さを感じさせた。
フィレンツェに変に舞い上がっている様子はなく、何より身持ちの堅そうなのが良かった。
これなら、編集長と宣伝部長を一緒に行動させても、変な間違いを起こすこともないだろうという安心感があった。
リヴォワールのテラス席に彼女らを誘い、編集長と宣伝部長を紹介してベネト産の発泡酒プロセッコで乾杯した。
明日、ピッティ・ウオーモの展示会を視察した後の13:00にウフイッツィ美術館を予約したこと、彼女たちと一緒に回ることを報告すると、編集長らはすこぶる機嫌が良かった。
こんな時、大手の出版社というのは有利だ。
彼女たちも、普段愛読している女性ファッション誌を発行している出版社の、メンズ総合誌の編集長と宣伝部長ということで、興味深々で話に夢中になっている。
編集長がしきりに目で合図を送ってきたので、今夜夕食をご一緒にいかがですか、と誘った。
喜んで、という返事を受けて、夕刻に彼女たちのホテルに迎えに行くこにとした。
パラッツオ・ヴェッキオの五百人広場を観に行くという二人と別れ、我々は昼食へと向かった。
予約したリストランテのブーカ・ラピ〈Buca Lapi〉は、アンティノーリ宮の半地下にあるトスカーナの地方料理がメインの店で、特に炭火で焼くフィレンツェ風Tボーンステーキ、ビステッカ・アラ・フィオレンティーノが看板メニューとなっている。
アンティパスト〈前菜〉、パスタに続き、ワゴンに乗せられて登場した巨大なビステッカ・フィオレンティーノを前に、見慣れている私以外の二人から、おおーという声が漏れた。
カメリエーレ〈給仕〉が、大きな塊を切り分けて、各人の皿に取り分けてくれる。
毎度そうだが、あまりのボリュームにTボーンの骨側の肉まで食べ進めたことがない。
はたして他の二人もこれ以上は無理だと根をあげた。
カメリエーレは、ここからが旨いのにと言いながら、ワゴンを押してメインを退場させた。
ワインの酔いと、肉で満たされた腹に、ドルチェと食後酒のグラッパが最後のとどめを刺し、これで街が再び動き出す16:00まで、大概の人は思考停止に陥るという幸福な時間を過ごす。
イタリア名物〝お食べ地獄〟に嵌まり、もう動けないという、虚ろな目をした編集長らを、私の宿泊する丘の上のホテルに案内することにした。
パオロの待つレップブリカ広場まで歩き、彼のタクシーで再びベッロ・スグアルド通りを上った。
朝のプールサイドの特等席とプロセッコを手配して、彼らが絶景に呆けている間に、部屋に戻ってディナーのリストランテの手配と、いくつかの電話をかけてから、簡単にシャワーを浴びて酔いを飛ばした。
プールサイドに戻ると、二人は心地好さそうに夢の中にいた。
腹がくちいところへ、酒の酔いと初夏の心地よい風、プールの水のゆらぎの前で睡魔に抗える人間は多くない。
30分ほど邪魔をせずにおいて、エスプレッソを運ばせて二人を夢から引き戻し、再びチェントロ〈市街〉へと戻った。
チェントロでは、トルナヴォーニ通りの高級ブランドのブティックを巡り、二、三の仕立て屋や皮職人の工房を紹介して彼らのホテルに戻った時、二人の両手には、またしてもブランドのショッピングバッグがぶら下がっていた。
そしてすでに彼女たちを迎えに行く時間が迫っていた。
彼らが戦利品をホテルの部屋に運び込んでいる間に、待ち合わせをしていたカメラマンのルカがやってきた。
カメラマンとしての腕も確かだが、この男も時間に正確であるところが気に入っている。
イタリアではとても大切なことだ。
ディナーを予約したリストランテは、キャンティ近くの郊外にあり、人数も増えてパオロのタクシーだけでは足りないので、ルカの車も駆り出した。
もともと郊外のリストランテはルカの紹介であったし、明日以降の仕事の打ち合わせも兼ねている。
陽子と智美は、今日買ったばかりらしい黒いワンピースにハイヒールを履き、肩にエトロのペイズリー柄の大判のシルクシフォンのストールをかけホテルのバールで待っていた。
我々が到着するまでの間、確実に複数のイタリア男が声をかけているに違いない。
それを楽しみながらも、さらりと受け流す余裕があるように見えるところが、この二人の魅力となっている。
パオロの車に彼女らと編集長らを乗せ、私はルカの車に同乗し、ルカがキャンティ郊外のリストランテまで約1時間の道のりを先導した。
春から夏の期間だけオープンする「農家」という名の、この野外リストランテには、広大な敷地の真ん中に巨大な白いテントが張られ、その中にあるテーブル席には百人ほどが収容できるようになっている。
眼前には、キャンティの丘に糸杉に囲まれたオリーブと葡萄畑が広がる。
テントの中心にある支柱の周りには、この時期にこの地方でしか食べることができない食材の惣菜が大皿に盛られていて、アンティパストは、この大皿から自由に取り分けて食べる。
私のお気に入りは、イチジクと生ハムで、熟れきった酸味のあるイチジクと生ハム、それにあわせたキャンティワインのマリアージュは絶品であった。
彼女たちにも、編集長らにも気に入ってもらえたらしく、宴は続き瞬く間にワインが3本ほど空いた。
ゆっくりとドルチェと食後酒を味わって、フィレンテェ市内に戻ると時計は23:00を回っていた。
四人でホテルのバーで飲みなおすからという編集長ら一行、帰宅するルカと別れて、パウロのタクシーで丘の上のホテルへ向かった。
編集長らは玉砕するだろうな、と独り言ちると、パウロが日本語にも関わらず、男の感で判ったのか、ハッハッハッと嗤った。