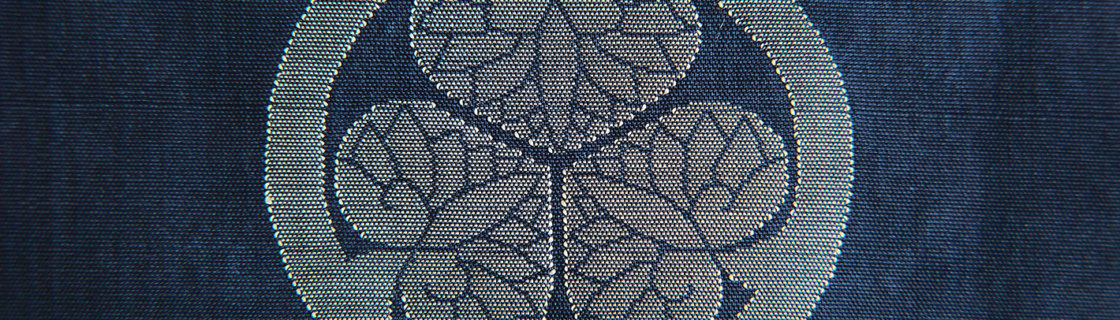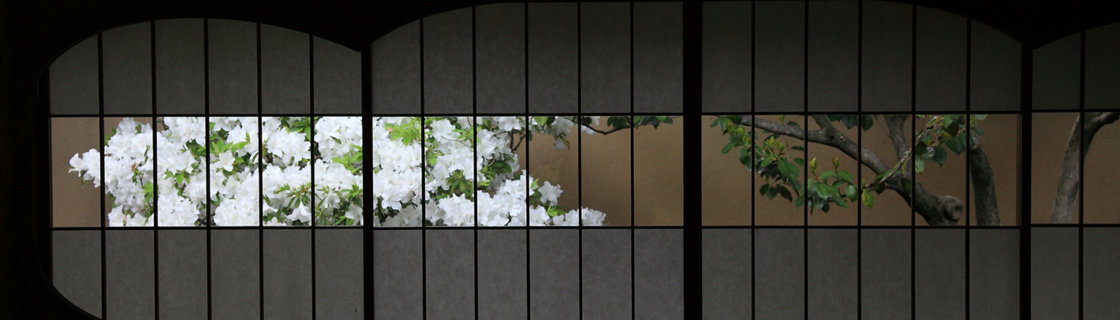夢魔の棲まう街 その七

朝食 Breakfast
二階の朝食用の食堂に降りると、窓際に一組の老夫婦が座っているのみで、どうやら私が朝食を摂りにきた最後の泊まり客らしい。
白いエプロンに黒いワンピースという古式ゆかしい姿の給仕の女性が、ボンジョルノ〈おはよう〉外のベランダにする、それとも中にする、と聞いてきた。
私はこんなに気持ちの良い日は当然、ベランダで、と元気よく答えた。
その時、老夫婦は顔を見合わせて微笑んだようだった。
その微笑みが気になりながらも、誰もいないベランダのテーブルに着き、カフェラッテとガス(炭酸)入りの水、アランチアータ(赤いオレンジジュース)に目玉焼きを注文した。
ベランダの下には、なだらかな丘陵地の糸杉に囲まれてオリーブが点々と植えられ、そのずっと下の方には葡萄畑が広がっていた。
手前の糸杉の下で馬が草を喰(は)んでいる。
逃げないのかなと心配していたら、目立たぬように柵で囲ってあった。
低く頼りない柵であったから、馬にも逃げる気がないのだろう。
チェントロ(街中央)から二十分足らずでこの景色は贅沢すぎる。
こんな景色を満喫せずに、中の食堂で朝食をすますとは、変わった人たちだな、と思っているところへ、給仕がブリオッシュ(砂糖のまぶしてあるパン)が置かれた皿と、蜂蜜と数種のジャムの小瓶が乗った器をテーブルに置いた。
二分後、私は食堂の中で食べるべきを知った。
蜂である。
蜂蜜の瓶とジャムの瓶、砂糖だらけのブリオッシュに一斉に蜂が群がってきた。
一匹や二匹ではない、十匹以上の蜂が私のテーブルの廻りで乱舞している。
たまらず食堂の中に逃げ込んで、思わず給仕に、中で食べます、と叫んでしまった。
私の言い方が面白かったのか、老夫婦が小さく声を立てて笑っている。
その笑いが、暗さのない笑い方だったので、私も冗談めかして、顔を思いっきりシカメながら老夫婦の隣のテーブルに腰を下ろした。
老紳士は、いやあ、君も洗礼を受けたね。
私たちも最初の朝は同じ目にあったよ。
あの給仕の女性はマリアというんだが、毎朝ベランダを選んだ客に、わざと蜂のことを伝えずに案内する。
そして、前日被害を受けた客は、次の日に繰り広げられるその光景を楽しむということが、申し送りのように続いているのだよ。
くれぐれも怒らないようにね、と嬉しそうに秘密を打ち明けた。
この〈秘密の打ち明け〉も毎朝の儀式なのだろう。
夫人もうなづきながら、お願いねと、くすくす笑った。
マリアがベランダから蜂の獲物一式を、移動した私のテーブルに並べた。
私が、再び大げさなしかめっ面でマリアを見ると、彼女は、これまた大げさなウインクを返して厨房に消えた。これで本日の朝食の儀式は終わりのようだった。
蜂たちも食堂の中は縄張り外なのか、入ってこなかったが、なおも自分の仕事に忠実で行儀の悪い一匹が、果敢にジャムの瓶を狙いにきて、こいつは老紳士のタバコの煙一吹きで退散していった。
老夫婦は、ドイツから来たと云った。
これから半月をかけて、車でトスカーナのワイナリー巡りをするのだという。
今日は夕方までにグレーヴェ・イン・キャンティGreve in Chiantiまで行けば良いのでゆっくりだという。
有名なワインの産地キャンティは、フィレンツェから二時間たらずの場所にある。
 キャンティ・クラシコのシンボルマーク 黒い雄鶏〈GALLO NERO〉
キャンティ・クラシコのシンボルマーク 黒い雄鶏〈GALLO NERO〉
グレーヴェ・イン・キャンティは、ワイン産地の中心地にある街で、こぢんまりとした広場にはエノテカ〈ワイン専門店〉や、飲食店、バール、雑貨屋、八百屋、薬局、郵便局などがひと通りあり、広場の中央には、アメリカ西海岸を探検した初めてのヨーロッパ人とされるジョヴァンニ・ダ・ヴェラッツアーノGiovanni da Verazzanoの彫像がたつ。
この広場では、毎年九月にキャンティ・クラシコ協会主催のワイン祭りが開催され国内外の大勢の人で賑わう。
この頃のイタリアでは、農家に体験宿泊をするアグリツーリズモが盛んになりつつあった時期で、大中の農園主が、宿泊用に農園内の納屋を改装したり、新しく小屋を建てたりしていた。
中には立派な食堂やプールを備えている処もある。
宿泊用の小屋には四、五人が泊まれて、自炊ができるようにキッチンやダイニングの設備と食器やグラス類が用意されているのが一般的なようだった。
老夫婦には、これから半月の間、昼にワイナリーを巡って、ワインやオリーブオイルなどを購入し、夜には、地元の店で調達した肉や野菜、パン、パスタなどを料理して、購入したばかりのワインを呑りながら味わうという、誠にうらやましい旅が待っている。
老紳士は、しきりに肉には「キッコーマン」が一番だと親指を立てる。
私も、ステーキには、塩胡椒と醤油があれば何もいりませんよね、と返す。
そういえば、以前キャンティを廻った際、日本料理から最も遠い野中の一軒家みたいな食料品兼雑貨屋に「キッコーマン」を見つけた時は、流石に美味いものに妥協のないイタリア人と、妙に感心したのを思い出した。
老夫婦と別れてレセプションに降りると、夜勤明けのジャンニに出喰わした。