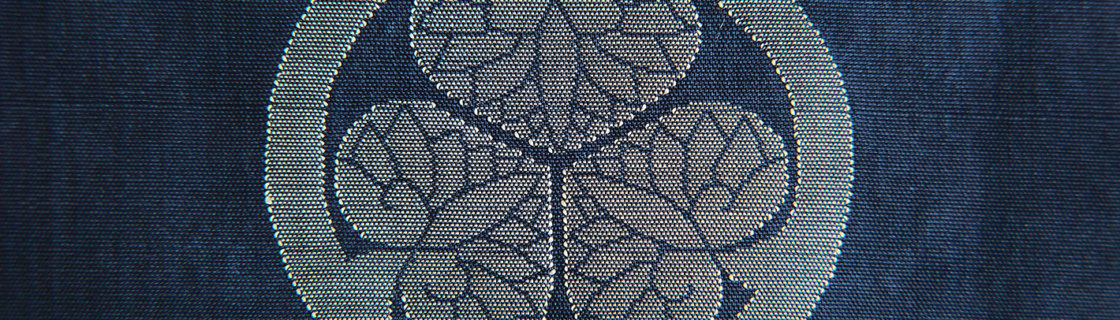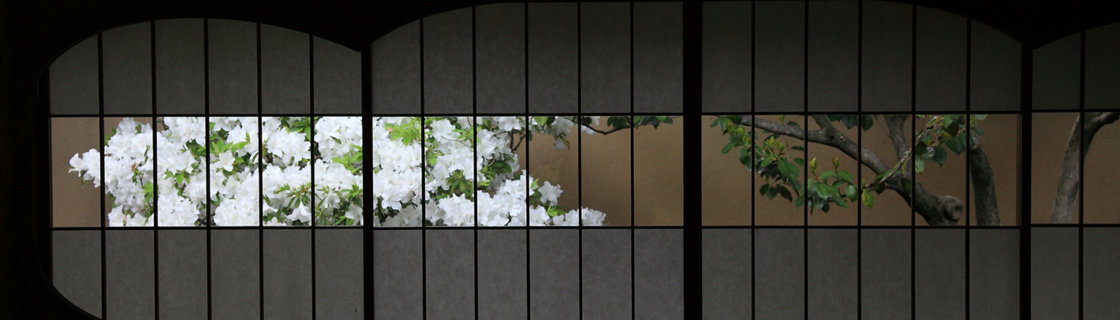夢魔の棲まう街 最終話

チェックアウト Check Out
窓の下には、いつもの馬が糸杉の下にいる。
お前は昨日の夜はどこにいた。
声に出さずに尋ねた。
私の無言の声を聞いたのか、馬は一瞬こちらを向いたが、またすぐに草を喰み出した。
少し腰がふらついたが、シャワーを浴び、食堂に降りて朝食を摂った。
階段の定位置にいたグレイの猫が、今朝は啼きもせず、私の顔をじっと見つめていた。
鞄に荷物をまとめてドアを開け、ベッドと部屋を振り返る。
たった一夜寝ただけなのに、誰かを残して部屋を出て行くような感覚に襲われた。
チェックアウトのためフロントに降りると、ジャンニがアンティーク机の前に立っていた。
どうしたことか、ジャンニの顔からは血の気が失せて、青白き蝋色をしていた。
チェックアウトも上の空で、クレジットカードの控えを差し出しながら、私に、カフェを呑まないかと聞いて来た。
パオロが迎えに来るまで少し時間があったので、バールに付き合った。
ジャンニは、もう耐えられない、今日でホテルを辞めるという。
彼はエスプレッソに気つけのグラッパを入れながら、このホテルでは彼のように夜勤専門で雇われた従業員がつぎつぎ辞め、ジャンニが知る限り、彼で四人目になるのだと明かす。
彼が告白するには、実は、ほぼ毎夜雷雨が襲うという。
それも、このホテルにだけ、いや、このホテルに滞在するある者にだけ、最初の頃は、ジャンニも次の日誰彼なしに、昨夜の雷雨は凄かったねと聞いて回った。
しかし、皆が異口同音に、いや昨日の夜は雨なんて降っていないと答えるのだった。
同じ質問を数日続けたところで、他人が訝しげな視線を送って来るようになったので、聞くのを止めた。
それでも雷雨は続く。
すると私のように同じ質問をしてくる宿泊客がいた。
昨夜の雨はひどかったね。
しかしながら、それは全員ではないという、ある者にはひどい雷雨が、またある者には穏やかな星空夜が訪れるようだった。
それと知れるようになってから、ジャンニはその質問をしてきた宿泊客には不安を与えぬよう、いえ昨夜は雨は降っておりませんが、と答えるようにしたという。
だから私の問いにも同じように答えた。
だが、昨夜はいつもと違った。
雷は止むことがなく、激しさを一層増し、放たれた稲光でフロントのホールはいつまでも明々と照らし出された。
普段は薄暗い天井のフレスコ画までが、はっきりと見てとれたという。
終わりなき雷光に身を縮め怯えていると、左奥の壁がぼーっと光り、そこに描かれた三美神の一人が壁からすうーっと抜け出して来た。
彼女は、ジャンニの座る机の前を滑るように過(よぎ)って、首だけを捻ってジャンニに一瞥をくれてから、階段をゆっくりとした足取りで階上に消えた。
やがて、階段にいるグレイの猫がにゃあーと啼き、その前を通ったのが知れた。
壁には二人の美神しかいない、それが三人に揃ったのは明け方近くで、階下におりて来た彼女はゆっくりとまた壁に収まったという。
彼女がフレスコ画に戻った途端、雷雨は止んだらしい。
ジャンニは私に、昨日の夜はどうだ雨は降ったか、何か感じなかったかと聞かれたが、今度は私がジャンニのために、いや昨夜はいたって平穏な夜だったよと答えた。
昨日のような夜を過ごすのは二度とごめんだ。
今日でホテルを辞めるんだという顔色の失せた彼に、かける言葉はなかった。
パオロが迎えにやって来たので、カフェを飲み干しジャンニに別れを告げて、ベッロ・スグアルドの坂を下った。
坂の両脇は相変わらず初夏の陽気の中、呑気に萌え盛る緑に覆われている。
その溢れかえる生命力を吹き出している緑は、今朝の私を噎(む)せ返した。
イタリアの通貨がユーロになって十数年になるが、私は相も変わらず年二回フィレンツェを訪れている。
あの晩以降、丘の上のホテルに宿泊することも訪ねることも二度となかった。
ホテルが繁盛しているという噂も聞かない。
あれからパオロの髪型と髪色は目まぐるしく変わったが、彼女ができ所帯を持って子供が生まれてから、ようやく今のスタイルに落ち着いた。
しかし、耳のピアスは相変わらずだ。
今でも度々貸切の仕事を頼む。
タクシーの仕事は性に合っているようで、このままずっと続けて行くのだろう。
ジャンニは、トルナヴオーニ通りのセレクトショップのスタッフとなり、今ではドゥオーモ近くの支店を任されている。
私がフィレンツェを訪れるたびに、滞在中一度はランチかディナーを必ず共にするのが二人の取り決めのようになっている。
長く付き合っているパートナーはいるが、結婚はまだ先のようだ。
最近、そろそろあの夜の本当の出来事を話そうかと思っている。
了