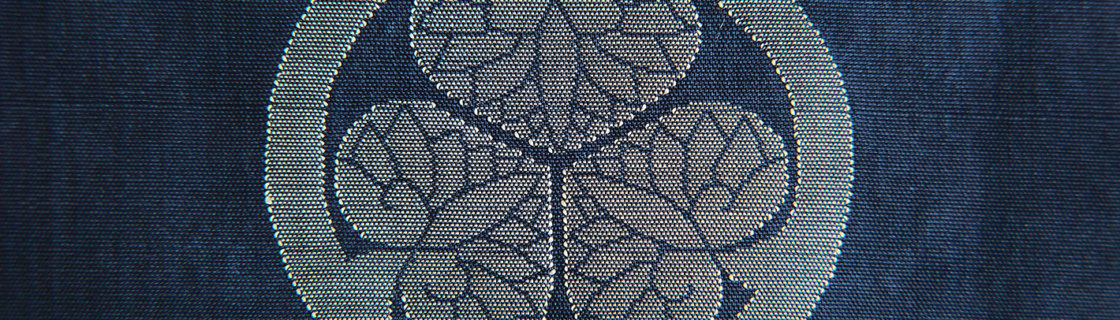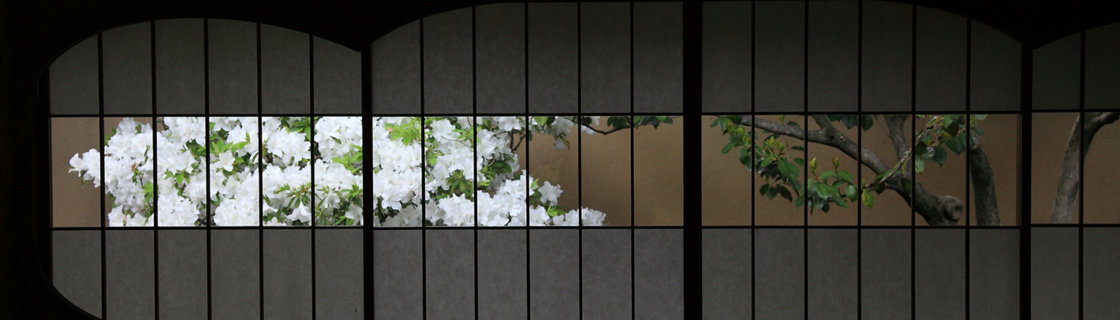夢魔の棲まう街 その十一

夢魔 Wet Dream
パオロの車がまたベッロ・スグアルドの坂を上り、門を潜ってホテルへと辿り着いた。
ファサードで降りてから、明日の迎えの時間を確認して、パオロと別れた。
そしてまた、丘の上の館に影を纏った夜がやってきた。
ホテルに入って、アンティークのフロントデスクに座るジャンニと挨拶を交わし、鍵を受け取る。
今日はどうだったと問う彼に、午後に来客をふたりプールサイドに案内して喜ばれたことや、キャンティ郊外のレストランテも評判が良かったことなどを話していると、もうクローズしているはずのバーから、プロセッコでも持ってこようかというのを制して、もう寝るよと階段を上り始めた。
私を引き止めて、まだまだ話したいという素振りだったが、明日からが仕事の本番の私は、少しでも睡眠を取りたかった。
ジャンニは、私と話したいというよりも、広いホールに一人残されたくないという気持ちが強い風だった。
階段の上には、昨夜も今朝も同じ位置から私を見下ろしていたグレイの猫がいて、今夜はニャーと低く長く啼いた。
その啼き声が、石造りの階段の薄暗い空間をゆっくりと満たし、冷んやりとした風となって私の背中を伝った。
部屋に戻り、バスタブに熱めの湯を張る間に、明日ピッティ・ウオーモで廻るブランドメーカーの確認と、午後に案内するウフィッツィ美術館の名画の説明を簡単に追った。
ゆったりとしたバスタブにゆっくり浸かって湯の温もりを体の芯に感じてから、天蓋付きのベッドへと潜り込んだ。
そしてまもなく深い眠りについた。
どのくらい寝た頃だろう、激しい雷鳴で目が覚めた。
号砲のような一撃の後、止むことなく雷が鳴り響く。
絶え間無く続く稲光のせいで、もはや昼間のように明るくなった。
だがこの明るさは、暗闇よりも邪(よこしま)なものたちの棲まう寝ぐらのように思え、その者たちの登場を知らせるかのように、雨と風は踊り狂う。
窓の白いレースのカーデンが狂おしく舞っている。
恐怖が胸を襲い、窓を閉めに行く勇気さえ出ない。
シーツに潜り込んで光から逃れようとした。
それが呼び水となったようだ。
ベッドの端が軋んだ。
足元から何かが潜り込んでくる気配がした。
私の上を這う何者かの軀を感じた。
意識は覚醒しているのに、躰が硬直して自由がきかない。
シーツの中を、栗色の長い髪が私の躰を撫でるように上がってくる。
太腿に、下腹部に、臍に、乳首に、髪が触れるたびに私の胸は波打った。
滑らかな肌は、ジノリのベッキオホワイトの磁器のごとく冷んやりとしていた。
私の唇、鼻、目、額を栗毛が愛でてから、彼女の顔が現れた。
黒く細い眉、ブルーのインクが溢れる瞳が私を見おろす。
口を重ねるでもなく、私を凝視しながら
乳白の肢体は獲物を探り、やがて捕らえた。
そのまま私の両の手を握り横に広げると、片方の手で私の肩を抑え、もう一方の手で顎に掌を当て私の口と鼻を上から押さえた。
馬乗りになった彼女のふくよかな太ももと臀部、そして下腹部が、私を包み込んで離さない。
たわわな乳房が私の胸に重なっている。
足の付け根は固定され、彼女に覆われていた。
私を迎え入れると、腰を動かすでもなく、中で濡れた壁が蠢(うごめ)く。
その中だけが、荒ぶる精霊のように、ひたすら熱く熟れていた。
幾度も幾度も精を放った。
声にならぬ絶頂の叫びを何度もあげた。
やがて意識が飛んだ。
朝が来た。
やはり、夜半の雷雨が嘘のように、窓から穏やかな初夏の日差しが差し込んでいる。
あれだけ濡れそぼり、風に乱れたカーテンが、陽光に一層白く輝いている。
何度も精を受け止めたはずの下着は汚れていなかったが、シーツは二人分の寝乱れた痕を残していた。